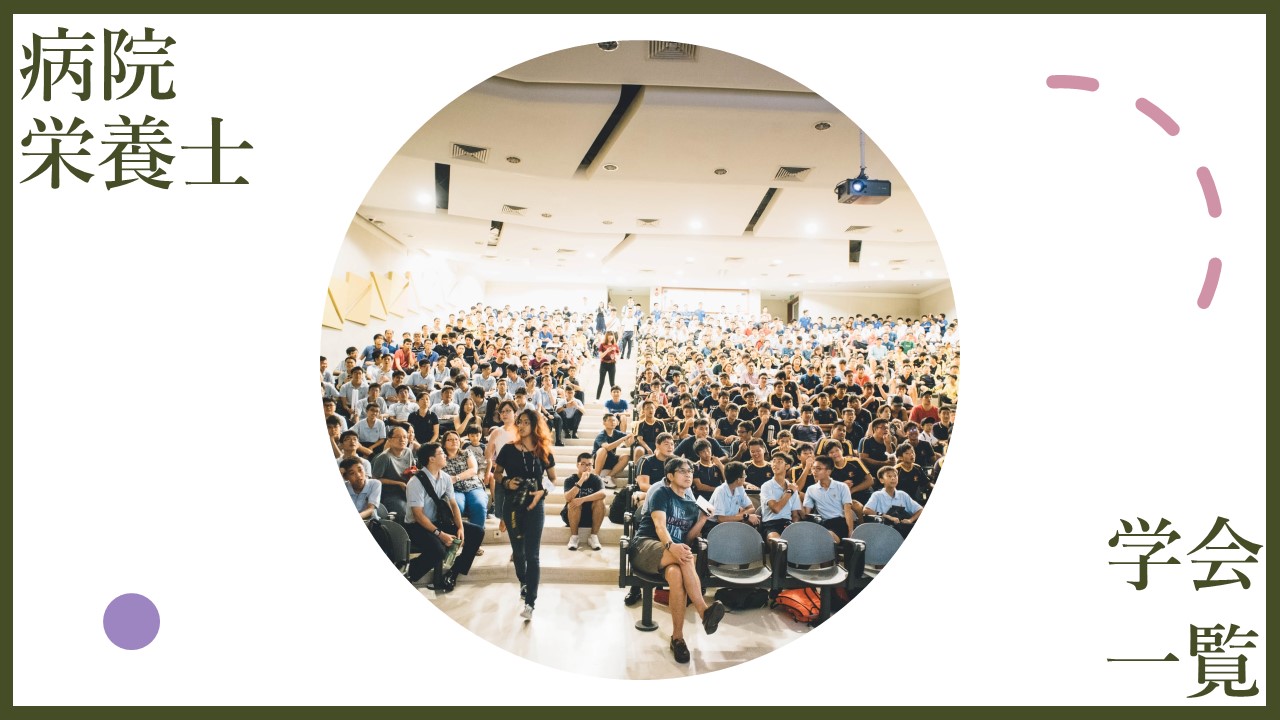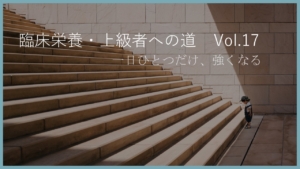臨床栄養をもっと学びたい。でも、栄養の学会はどんなのがあるか分からない。こんな経験は少ないけど、向上心はある方向けの記事です
✓本記事の内容
病院で働く方へおすすめする臨床栄養系の学会5つ
この記事を書いている私も、過去にどの学会に入るか悩みました。栄養士として働き臨床栄養系の学会に10年以上在籍していますので、迷っているかたへの記事を書きました
日本のメジャーな臨床栄養系学会を5つ、①年会費、②学会誌の発刊頻度、③認定資格、④コメント、の4項目で紹介します
臨床栄養系学会5つ
日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)
- 年会費:9,000円
- 学会誌の頻度:4~5回/年
- 認定資格:あり
NST専門療法士をはじめ、栄養士が取得できる学会認定資格が沢山あります。
通称JSPEN、旧静脈経腸栄養学会ですね。
会員数が約2万人で、臨床栄養系の学会では世界有数です。入院患者さんの栄養管理、静脈経腸栄養の情報が多いです。
日本病態栄養学会
- 年会費:10,000円
- 学会誌の頻度:4回/年
- 認定資格:あり
病態栄養専門管理栄養士をはじめ、栄養士が取得できる学会認定資格が沢山あります。
会員数は約9千人で、医師と栄養士(管理栄養士)が大半です。糖尿病などの生活習慣病の情報が多いです
日本臨床栄養学会
- 年会費:9,000円
- 学会誌の頻度:4回/年
- 認定資格:なし(医師の認定資格あり)
栄養士が取得する認定資格はありませんが、学術的な条件をクリアすると「認定臨床栄養学術師」という資格はとれます。
会員数は約千人で、医師と栄養士(管理栄養士)が多いです。食品系・生活習慣病系など情報の幅は広いです
外科代謝栄養学会
- 年会費:9,000円
- 学会誌の頻度:4回/年
- 認定資格:なし(医師の認定資格あり)
栄養士向けの認定資格はありません。
会員数は公開されておらず、不明ですが学術集会の雰囲気からそんなに多くは無いのかな?と思いました。
医師が会員の大半を占めていると思います。消化器外科の周術期栄養管理の情報が多いですね
日本リハビリテーション栄養学会
- 年会費:10,000円
- 学会誌の頻度:2回/年
- 認定資格:あり
栄養士が取得できる認定資格として、「リハビリテーション栄養指導士」があります
会員数は2018年時点で6千人、もっと増えていると思います。会員構成は医師・歯科医・看護師・リハビリ・栄養士・歯科衛生士など多彩。
リハビリテーション+栄養についての情報が多いですね。
その他の学会
メジャーとは言い難いですが他にもあるので、日本でよく紹介される海外の臨床栄養系の学会と併せて示しておきます
- 日本健康・栄養システム学会
- 欧州臨床栄養代謝学会(ESPEN)
- アメリカ静脈経腸栄養学会(AEPEN)
どの学会に入るか悩んでいたら

もしこの記事を読んでいるあなたが、病院栄養士でどの学会に入るか悩んでいたら、私のオススメは下記の4学会
- 日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)
- 日本病態栄養学会
- 担当診療科に関係する学会
- 興味のある栄養系学会
理由は下記を考慮したからです。
①学会費・資格の維持費、②日常的に役に立つ情報が入る、③栄養士としての知識の底上げ
担当診療科に関係する学会とは、集中治療医学会や糖尿病学会などです。そこの学会が出しているガイドラインに栄養療法の項目があれば尚良いと思います。日常の業務に直結する情報が得られます。
興味のある栄養系学会とは、日本栄養・食料学会や給食経営管理学会です。臨床以外にも栄養士として食品や栄養素、調理の情報を得られるからです。栄養以外でも興味があれば知識の吸収も早いので入ればいいと思っています。
勉強するために学会にはいる?
もし、インプットだけのために学会へ入会するつもりでしたら、あまりオススメ出来ません。
なぜなら、論文はPubMedやJ-STAGEに読み切れないほどありますし、専門性を磨くなら「臨床栄養」などの専門雑誌があります。ガイドラインはMindsや各学会のホームページで読める事も多いからです。
効率的・系統的に知識を得るにはいいかもしれませんが、であれば専門の入門書を読めばいいと思います
「認定資格を得たい」「役職に就いて臨床栄養の業界を盛り上げたい」等、学会誌を読む以外の目的があれば入会をオススメします。学会に入る理由を明確にできれば必然的にはいる学会も決まってくると思います
おしまい