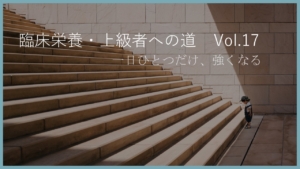病院で働いて栄養管理の経験は積んできたけど、自分の職場で経験が得られない栄養の知識を得たい、教科書よりもっと知識を深めたい・・・。
こんな向上心の高い栄養士向けの記事です。
本記事では、病院で働く栄養士に向けておすすめの栄養関連雑誌を紹介します。
結論:「臨床栄養」+「Nutrition care」+担当診療科の専門誌
栄養士として10年以上働いている管理人の都(みやこ)がおすすめする栄養雑誌をまとめて紹介していきます。読者としての私が魅力を感じた雑誌のみを紹介しています。
「 臨床栄養 」
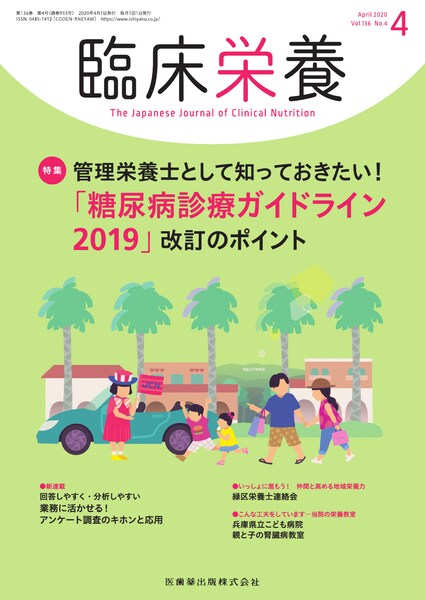
1つ目は臨床栄養雑誌の王様、「臨床栄養」です。1952年に創刊された歴史ある雑誌で 医歯薬出版株式会社が発刊して います。 栄養の分野では有名な雑誌です。 もうこの一冊で良いと言えるくらい充実した内容で、私は病院栄養士には必須と思っています。定価 1,600円+税
内容を大まかに分類すると下記の4つで構成されています。
- 特集
- 栄養士の取り組み
- 連載記事
- 栄養業界インフォメーション
特集
毎号、何か一つをテーマに特集が組まれています(例えば心不全診療等)。そのテーマで活躍されている先生が執筆されているため、最新の情報から総論・各論と網羅的にまとめられています。
記事の情報は、現場の栄養士でも読みやすいよう広く、ガイドラインや学術的な内容も含みながら執筆されています。社会人一年目からベテラン栄養士まで、幅広い世代におすすめします。記事に登場する図表も含め引用が充実しており、気になった個所はさらに深く調べることが出来ます。私は「臨床栄養」 のコアはこの特集記事だと思っています。
「臨床栄養」を購入したときには重要性を感じなくても、数年後にこの特集が自分の疑問を解決する窓口になってくれます。捨てずに置いておきましょう。
栄養士の取り組み
地域の栄養士の集いや〇〇病教室など、栄養士の実際の取り組みが紹介されています。
「臨床栄養」は特集→栄養士の取り組み→連載時期→栄養業界インフォメーションと構成されています。色々な栄養士の方々のリアルな取り組みが記事にされていて、難しい文章はほとんどありません。とても読みやすく勉強になる記事です。栄養士の取り組みの記事は「特集」を読み終わって、使い切った脳が休まります。
連載記事
実際の献立紹介や一人の先生が文字通り連載されている記事で構成されています。
献立はとても勉強になりますし、アイデアに驚かされることもあります。大阪の井上先生が連載されている記事があるのですが、読みやすく勉強になります。
栄養業界インフォメーション
学会の情報や開催スケジュール、栄養に関するニュース、研修会のお知らせ等が掲載されています。自分が知りたかった内容がコンパクトにまとめられている事が多く、私は目を通すようにしています。
手元にある「臨床栄養」のページ数を確認すると130ページありました。良いボリュームです。 年に2回発刊される増刊号は教科書並みのボリュームで、内容も深いです。もしまだ読むべき栄養雑誌を決めていない方はぜひ「臨床栄養」を購読することをおすすめします。
「 Nutrition Care 」

2冊目は「Nutrition Care」です。比較的新しい雑誌で、メディカ出版より2007年に創刊されています。卒後3年目ぐらいまでをターゲットに置いた誌面作りをされている印象で、全体的にとても読みやすいです。図表もシンプルで可愛いイラストもあります。定価1,800円+税
内容を大まかに分類すると下記の3つで構成されています。
- 特集
- 栄養士・施設の取り組み紹介
- 連載
特集
毎号、何か一つをテーマに特集が組まれています(例えば心不全診療等) 。「臨床栄養」とは異なり、現場で働いている先生が執筆されています。これにより、実務に近い誌面に仕上がっています。引用文献は少なめですが、エビデンスのない事についても触れられているので、すぐに実臨床で使えます。テーマに沿った症例提示が多く、現場で使えるイメージがわきます。
「臨床栄養」と同じく、私はこの特集の記事が 「Nutrition Care」 のコアと思っています。たまに生化学などの基礎を特集される事もありますが、シンプルな図表と文章なので教科書よりもより理解しやすく、あなどれません。
栄養士・施設の取り組み紹介
毎号、栄養士一人にスポットがあたり、仕事・プライベートともに紹介されます。写真が多く親近感がわきます。レシピ紹介もあります。 一度出てみたいですね。
連載
連載は0.5~4ページとコンパクトにまとめられていて、しかも沢山の記事があります。本当に読みやすいです。栄養以外の連載もあり、自分の知らない分野の知識もつきます。私は丸山先生が連載されている「世界の術後食&病院食」がとても好きです。
手元にある「 Nutrition Care 」のページ数を確認すると104ページありました。コンパクトで読みやすいので 「臨床栄養」がむつかしいと感じた方は 「Nutrition Care 」 をお勧めします。 増刊号も年に数回発刊されます。 特集記事が1~2年で”一周”します。とはいえ、10年以上栄養士をしている私でも、いまだにお世話になっています。
その他、おすすめの雑誌
栄養士の都(みやこ)がおすすめするのは「臨床栄養」「Nutrition Care 」の二冊ですが、それ以外にも良い雑誌はあります。下記の3冊です。順番に紹介していきます。
- ヘルスケア・レストラン
- 栄養経営エキスパート
- 栄養学レビュー
ヘルスケア・レストラン

日本医療企画が発刊している雑誌で、施設・病院栄養士向けです。給食や食品についての記事が充実しています。近年は臨床栄養の記事も増えてきました。特徴はひとつの記事が1~4ページにおさまっていて読みやすいです。エッセイもあります。手元の「ヘルスケア・レストラン」を確認すると80ページでした。定価1,100円+税
栄養経営エキスパート
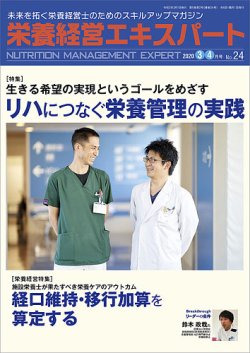
日本医療企画が発刊している雑誌です。雑誌名を見ると「おお!?」となりますが、内容は臨床栄養で、急性期病院の栄養士向けの記事が多いです。毎号テーマに沿って特集が組まれています。症例が多く提示され ています。「臨床栄養」「Nutrition Care 」 では組まれないテーマでも特集される事があります。
個人的には雑誌名に「経営」があるので”栄養士のための業績数字”みたいな記事が欲しいですね。手元の「栄養経営エキスパート」を確認すると78ページでした。定価1,500円+税
栄養学レビュー
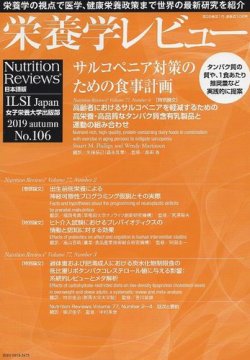
女子栄養大学出版部が発刊している雑誌です。今まで紹介してきた雑誌とは違い、季節に1冊発刊されます。 ページの大半がレビュー論文で 「Nutrition Reviews」という海外雑誌が邦訳されています。栄養素中心の内容で臨床の専門誌ではなく、栄養士・栄養学者向けの雑誌ですね。マニアックな内容で記事内の引用文献が50を超える事も多々あります。引用された文献を調べると永遠と勉強ができる恐ろしい雑誌です。
手元の栄養学レビューを確認すると96ページでした。93ページ目まで論文(笑)。定価2,100円+税
担当診療科の専門誌

最後に”担当診療科の専門誌”を読む事をおすすめします。具体的な例を挙げると「腎と透析」や「消化器外科ナーシング」などです。実はこの記事で一番伝えたいのはこの項目です。
なぜ、栄養以外の雑誌をすすめるかというと、今まで挙げてきた雑誌にも載っていない疾患に対しても栄養管理をするからです。栄養療法のエビデンスが無い疾患は沢山あります。でも、患者さんは事実いらっしゃる。となれば、病態を把握して栄養療法を自分で考えるしかありません。しかし、日々の疑問を解決しているだけでは系統的な知識はつきません。これらの問題を解決するために 「担当診療科の専門誌」 を読む必要があるのです。
例えば私は消化器外科で働いていますが、ドレーンの性状と量について栄養雑誌で特集が組まれているのを見たことがありません。でも、摂取している栄養でドレーン排液への影響はあります。したがって、ドレーンについての知識が必要と考えています。
おわり