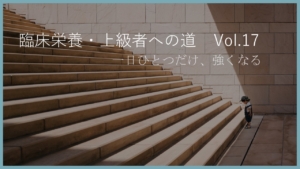病院で働きだして業務に慣れた。養成校時代の教科書では物足りなくなってきた3~4年目以降の栄養士向けの記事です。
この記事は私がTwitterで発信している「1日ひとつだけ強くなる」をまとめました。【226~250日目】
体系的ではありませんので、知らないトピックスがあれば、ご自身の学習を進める足がかりにしてただければ と思っています。1日目~はこちら
✔本記事の内容:臨床栄養のトピック25項目
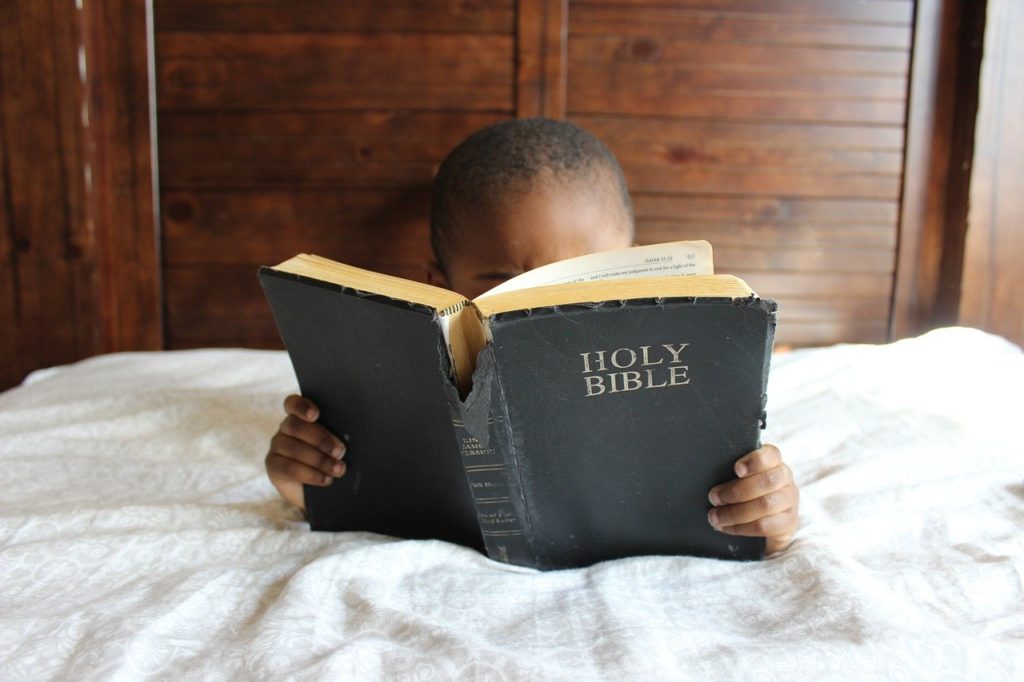
糖尿病診療ガイド2019:栄養素の摂取比率をどのように定めるか?
①予防・管理のための望ましいエネルギー産生栄養素比率を設定する明確なエビデンスは無い
②患者さんの活動量・併存疾患・年齢・嗜好を考慮して適宜
基準がない
本文中に少し記載あり
胆道メタリックステントの留置
・胆道狭窄や閉塞に適応される
太く拡張するのでチューブステントより開存期間が長い
ERCPの留置後3日程度で開ききる(らしい)ので、それまでは膵液胆汁が沢山分泌される食事は控えた方が無難かも
食事摂取基準は一日あたりの数値を示しているが、短期間(例えば1日)の基準を示していない。
理由は栄養素の摂取は日間変動が大きい事と、扱っている健康障害が栄養素の習慣的な摂取の過不足で起こるから。
昨日の食事を聞いて、そこだけ修正していくのはダメ
食事調査法プチまとめ
①食事記録法
②24時間思い出し法
③陰膳法
④食物摂取頻度法
⑤食事歴法
どれも長所短所がある。①は何日間とるかも検討が必要だし、施設環境ごとによってどれを採用するか…
習慣的な摂取を評価出来るのは④⑤。③は病院では無理
食事調査の過少申告
日本人の研究でもエネルギーについては、男性11%、女性15%の過少申告がある。
BMIが低いと過大申告、BMIが高いと過少申告する傾向だそうだ。
しかし、これはヒトの性質であって悪意は無いと思います。食事内容って記憶に残りにくい
炭水化物の摂取量は糖尿病の管理にどう影響するか
炭水化物摂取量と糖尿病の発症リスク、糖尿病の管理との、関連性は示されていない
最近のコホート研究では炭水化物摂取量と糖尿病の発症には関係が無く、果糖の過剰摂取が糖尿病のリスクを増した
ネフローゼ症候群
一日あたり量
■食塩→6g未満
■タンパク質
・微小変化型→1.0〜1.1g/IBWkg
・微小変化型以外→0.8g/IBWkg
■エネルギー
35kcal/IBWkg
減塩は浮腫、尿タンパクの改善に。タンパク質制限は十分なエビデンスなし
習慣的な摂取量の±10%の範囲に入る摂取量を個人で得るために必要な食事調査日数
★エネルギー
【女性】
30〜49歳 4日間
50〜69歳 3日間
【男性】
30〜49歳 4日間
50〜76歳 3日間
秤量食事記録ですね。±10%という事は最大20%のひらきができるのか・・・
食事摂取基準の活用
栄養素の摂取不足を回避することが目的であれば、推奨量(目安量)と推定平均必要量を用いる。
推定した摂取量が推奨量付近もしくは以上であれば不足のリスクがほぼない。
推定平均必要量以下であれば不足の確率が50%以上なので是正を
高齢時の体重変化は意図しているかが鍵
高齢者の体重は、減少・増加・変動をした場合、維持していた者と比べて死亡率が増加する傾向と過去の報告があり有名だが、注意点としては、意図していた場合の体重適正化は死亡率を増加させない
院中の患者さんで、意識障害があるときの栄養的考慮事項
下記があれば何か出来る事があるかも
- ケトアシドーシス
- 肝性脳症(高アンモニア)
- 高血糖、低血糖
- 低ナトリウム
- 尿毒症
- etc
が、Na低いからINを増やせば良いと、単純ではない事に注意
食事摂取基準における目標とするBMIの範囲
男女共通
・18〜49歳→18.5〜24.9
・50〜64歳→20.0〜24.9
・65〜74歳→21.5〜24.9
・75歳以上→21.5〜24.9
沢山の観察研究から作られたけど、あくまでも参考値
軽症膵炎の食事再開目安
・腹痛の消失
・膵酵素(特にリパーゼ)が上限値の2倍以下
文献的には5〜7日で再開されるケースが多いとか。
もちろん、脂質は制限で。ONSを使えば脂質0でタンパク質とエネルギーを補充することもできる。
減量や肥満是正
肥満の高血圧予防では5〜10%の体重減少が有効とされている。
いきなり標準体重にしなくても良い
食事摂取基準におけるエネルギー必要量
「ある身長・体重と体組成の個人が、長期間に良好な健康状態を維持する身体活動レベルのとき、エネルギー消費量との均衡が取れるエネルギー摂取」と定義されている
短期はまた別定義があり
成人の基礎代謝簡易計算式
体重kg × 20→○○kcal
食事摂取基準の値をみると20〜22/kg/kcal内に大体収まっている
最低必要なエネルギーを聞かれた時は、これで回答
体内コレステロール
肝臓だけでなく、脳・神経・筋肉・皮膚などに分布。
体内のコレステロールの1/4は脳神経系に
アキレス腱にも多く含まれるため、家族性高コレステロール血症には血清LDLと家族歴に加えて、アキレス腱の肥厚が診断基準に
既往歴
過去にかかって、現在は治癒している病気。糖尿病や高血圧症は「現病歴」となる
栄養に影響があるかは、既往歴と原病歴では全く異なる。
今日は基本中の基本を再確認しました
学校で習った記憶無い
コレステロールはエネルギー源として利用できないのでTCか低値を示す時は
- 摂取量が少ない
- 合成が減る
- LDLによる回収(異化)が増える
- 排泄が増える
以上の理由から、低栄養のパラメータに使える。半減期は1-3日
修飾要素が(DL等)無いかは確認
長鎖脂肪酸で構成される中性脂肪は、小腸で吸収されたあと、リンパ管を経て胸管から肝臓へ運ばれて、肝臓で合成される
なのでリンパ漏のときにはリンパ液の循環を減らす目的で消化管からの脂質は摂取しないようにする。
食事摂取基準における短期間のエネルギー必要量は
「そのときの体重を保つ(増加も減少もしない)ために適切なエネルギー」
とされる。
摂取エネルギーが評価困難でも、体組成などに大きな変化がなければ、食事聴取に労力を投入しなくても良い
2型糖尿病患者のサルコペニアリスク因子
低アルブミン、BMI低値に加えて血糖コントロール不良
加齢による筋肉量が減少する一方で、内臓脂肪が増加して肥満とサルコペニアが共存する事がある
担がんの状態の高Ca血症
骨メタからの骨破壊は20%、悪性体液性高Ca血症(PTH、PTHrP異常)が80%だそうだ。
PTH→副甲状腺ホルモンで、CaやPを調整
PTHrP→副甲状腺ホルモン関連タンパク
病名ではなく病態で栄養を考えたい
初発のクローン病と小腸型のベーチェット病は診断が難しい。が、入院した時点で体重減少を認めて消化管が使えないと、診断が付く前からTPNのプランを検討する必要はある
今ある情報とJSPENガイドラインで対応
吃逆(しゃっくり)の対応
ENを施行する患者さんが吃逆を繰り返していると、嘔吐のリスクが上がっている
投与速度や容量、開始後のモニタが重要。半固形化は嘔吐時のリスク上昇
薬剤対応では柿のヘタ、コントミン、スルピリドなどがあるので薬剤師さんと相談
つづく