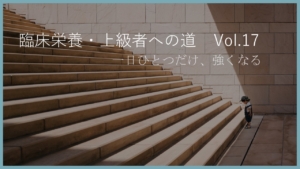病院で働きだして業務に慣れた。養成校時代の教科書では物足りなくなってきた3~4年目以降の栄養士向けの記事です。
この記事は私がTwitterで発信している「1日ひとつだけ強くなる」をまとめました。【201~225日目】
体系的ではありませんので、知らないトピックスがあれば、ご自身の学習を進める足がかりにしてただければ と思っています。1日目~はこちら
✔本記事の内容:臨床栄養のトピック25項目
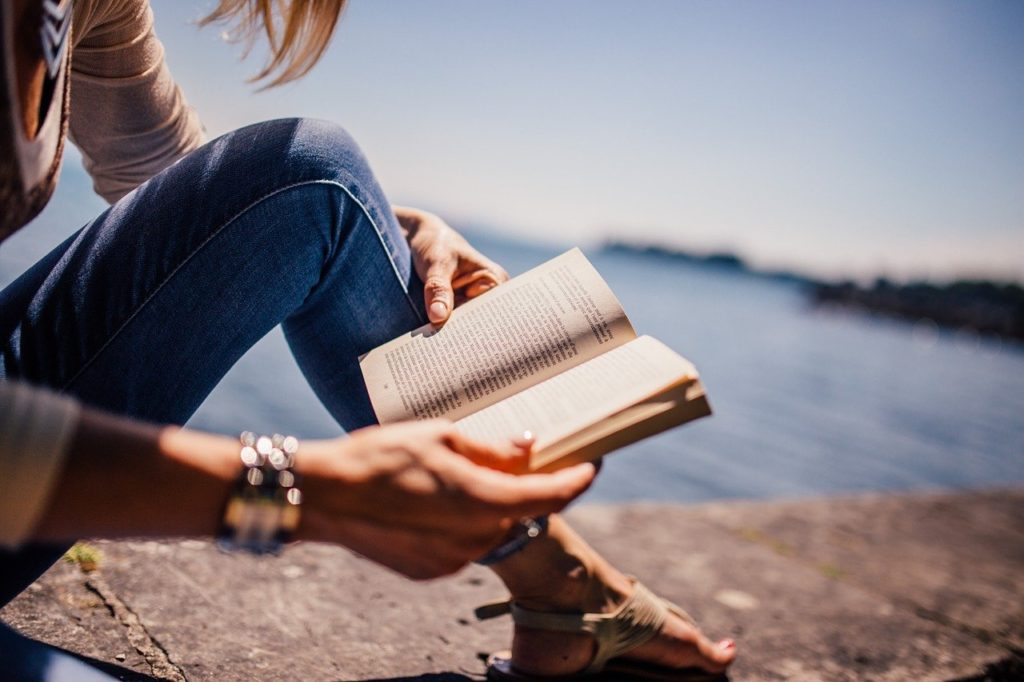
褥瘡の栄養
- エネルギー 30〜35kcal/kg
- タンパク質 1.25〜1.5g/kg
- vit A800〜900μg
- vitC 500mg以上
- vit E 8〜9mg
- 鉄 12〜15mg
- Ca 800〜1000mg
- 銅0.8〜1.0mg
- 亜鉛12〜15mg
- アルギニン7g以上
アルギニンがくせ者、食事での現状摂取量が不明だから。亜鉛⇄銅の拮抗に注意
褥瘡の栄養管理TIPS
- 鉄は血流確保や組織酸素運搬に重要であるため、不足しないよう
- ビタミンA、ビタミン C、Caはコラーゲン・架橋形成に関与。不足しないよう。
- ガイドラインに記載が無い栄養素は食事摂取基準に準ずる
「不足」に注意なので、盲目的に付加しない
サルコペニアの栄養
- エネルギーは多め 30kca/kg以上
- タンパク質 1.1g/kg以上
- ビタミンD 食事摂取基準量
サルコペニアのみで入院することは少なく、その疾患の栄養ガイドラインを考慮
過剰投与の兆候が無ければエネルギー・タンパク質は多めに投与
錐体路障害
運動神経線維(ニューロン)の遠心性経路で延髄の錐体を通る経路のことを錐体路といい、大脳皮質と下位の運動中枢である脳幹および脊髄とを結ぶ。らしい…
障害があると嚥下障害につながるので、評価→形態考慮
中心静脈栄養中は基本、脂肪投与
一般に、グルコース主体のTPNでは高血糖、高インスリン血症となる。
門脈血のインスリン・グルカゴン比が高いとインスリンの脂肪合成作用により肝に脂肪蓄積
栄養が輸液のみで脂肪の投与が無いと脂肪肝になりやすい。肝機能はチェックする
急性胆管炎の重症例
重症例とはショック・意識障害・臓器不全など予後不良因子をもつ症例のことで、日本のデータでは急性胆管炎のうち、11%が重症(研究によって変動)
症状によるが、ご飯を食べてる場合では無い
【付録】食事摂取基準
個人の評価で大問題
日間変動、前日の摂取エネルギーの差は平均600kcalもあった。
「1日間の摂取量を使えば指導のネタは尽きません、しかしこのような指導はしてはなりません」📝
食事記録を理解したい
【付録】食事摂取基準
食事摂取量≒申告摂取量×0.8
過去の報告から、男女ともに18〜50歳で約20%の申告誤差が起きている。(年齢ごとに違う)
エネルギーの過不足の評価はエネルギー摂取では無く、体重推移で行う。
食べた品だけを咎めるのはダメ
【付録】食事摂取基準
Q:推奨量の許容誤差はどのくらいあるか?
A:およそ±5%
基準の値はそもそも丸められている。使いやすいようにするためである。細部の違いにあまり意味がない
【付録】食事摂取基準
▽数値よりも信号の色で考える
良好 ▶︎青信号
要注意▶︎黄信号
要改善▶︎赤信号
現在摂取量をX、推定平均必要量をE、推奨量をRとすると、X<Eは赤信号。R<Xは青信号。
そして、狭間も考慮する
輸液のスペースは薬剤師さんへ相談
点滴での解熱剤が300ml入っており、TPNの水分スペースが足りず、栄養が不足してました。
後々になって薬剤師さんに聞くと、解熱剤を別の内服に変えられる事を知りました。
輸液の溶媒を減らせるケースもあるので、輸液の水分スペースに困ったら相談
消化管活動は食事を抜いてもリズムは維持
消化管の活動ピークは夕方となるため、減量目的で有れば夕食を控える、低栄養の是正は逆でとうだろうか。
ピークを示す時間帯(時刻) | |
| 味覚(塩辛味、甘み) | 朝 |
| 唾液の分泌 | 夕方 |
| 胃酸の分泌 | 午後8時ごろ |
| 膵液の分泌 | 夕方 |
| 二糖類消化酵素 | 夕方 |
| ビタミンB12の吸収 | 午後1時頃 |
| 鉄の生体内利用 | 朝 |
【付録】食事摂取基準
本当のエネルギー必要量は30〜40kcal/kg/日
多くのエネルギー消費量が30〜45kcal/kg/日の間に収まっている。40kcal /kg/日以上を示した対象者はほぼBMI25未満。
食事摂取基準
フレイル予防は推奨か目標か?
推奨量は当該栄養素の不足によって起こる健康被害が他の要因で起こらない
目標量は生活習慣病の予防を目的とし、生活習慣病には原因が複数
フレイルは蛋白不足以外でも起こるので、もし値が出来たら目標量に
【付録】食事摂取基準
総脂質より飽和脂肪酸
脂質はひとつの機能を持つ栄養素ではなく、共通した分子構造をもつ栄養素の集まり
飽和と不飽和は働きが異なる。n6とn3を目安量程度摂り、飽和脂肪酸を目標量より低く保つ
外科系のガイドラインではほとんど基準が無い
■栄養士の聴診
・腹部聴診に適した場所は腹部全体をヘソ中心に4分割し、右下の下腹部と言われている。場所は回盲部近く
■扱いの注意事項
・聴診器は清潔にする
・お腹にあてる前に手であたためる
・首にかけずにポッケにしまう
診断はしない。情報源
逆行性の胆管炎
乳頭括約筋が内視鏡的乳頭切開術(EST)などによりその機能が失われると、腸管から逆行性に胆管感染を起こしやすくなる。SSPPDの術後でも起きやすい
逆行性の胆管炎は胆管の器質的な閉塞が無い事が多いので、早めの経口再開が出来るかも
食事摂取基準は食物繊維は24g/日以上を目標としていますが、病気との関係を調べたメタ解析を見ると、それより少なくても疾患の発症率は下がりそう
ちなみに、食事摂取基準の値は食品由来なので、サプリで満たしても良いかは保証されていない
【付録】食事摂取基準
食塩の目標量、本当はおよそ1.5〜5.0g/日
不可避損失量は食塩相当量だと、1.5g/日摂取すればほぼ充分
目標量だけを厳しく守る事が、生活習慣病予防からの正しい事ではない。
軽症の急性膵炎の食事開始は液体より固形食
経口摂取開始時に液体食と固形食を比較した研究では、腹痛、再燃率は同等であるが、在院日数が短くなった報告あり。
患者さんの満足度も固形食の方が高いし、特段の理由がなければ固形食から
胆道ドレナージの正常量
→教科書的には300〜500ml/日
胆汁の一日分泌量と同じですね。いつものごとく、評価項目は単体では判断せずに、色調や変化量、他のバイタルと併せて検討材料に。
喪失する電解質も考慮。食事変更と合わせて廃液量も評価項目へ
消化液の分泌量(ml/日)
- 唾液→1,500
- 胃液→2,500
- 膵液→700
- 胆汁→500
- 小腸液→3,000
- 水様性の下痢便→500〜7,000
喪失している場合は電解質も考慮。水も飲んではいけない病態と言うが、(教科書的には)消化管にはこれだけ液体は流れている
食事摂取基準、数値は3つの目的と5つの指標から
①不足の回避
・推定平均必要量
・推奨量
・目安量
②過剰の回避
・耐用上限量
③生活習慣病の予防
・目標量
BCAAはアンモニアが骨格筋で処理される時に使われる
肝硬変でグリコーゲンが枯渇しやすい状態であると、エネルギー不足から、骨格筋も減って悪循環におちいる。
胃切除後の術式と逆流性食道炎
幽門側切除後のB-Ⅰ再建ではR-Y再建と比べで逆流性食道炎の発生が多い事が報告されている
食事の対策としては胃内に留まる時間が長い食品を避ける、一回量を減らす、症状出現時に少量の常温水を飲む、炭酸飲料を避けるなど
つづく