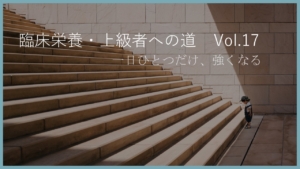病院で働きだして業務に慣れた。養成校時代の教科書では物足りなくなってきた病院栄養士向けの記事です
この記事は私がTwitterで発信している「1日ひとつだけ強くなる」をまとめました。【401日~425日目】
体系的ではありませんので、知らないトピックスがあれば、ご自身の学習を進める足がかりにしていただければ と思っています。1日目(Vol.1)~はこちら
✔本記事の内容:臨床栄養のトピック25項目

S状結腸軸捻転症
絞扼性イレウスのひとつ。わが国の発生頻度は全腸閉塞中2~7%との報告があり低い傾向に
治療は内視鏡による整復、手術がある。イレウス管を留置して減圧し軽快する事もある
栄養・食事療法は報告なし。再発予防についても不明
マンガン
体内含有量は12〜20mg
排泄は胆汁・膵液・尿
1日摂取量は2.5〜8.5mg
排泄経路により、胆道が閉塞してるときは入れない事もあり。
TPNのキット製剤に入っているのと入っていないのがあるため、念のため把握したい
栄養評価の臨床的意義
- 栄養障害の有無を判定
- 栄養障害の程度を把握
- 栄養管理の適応を判定
- 栄養管理法を選択
- 栄養療法の効果判定を定期的に行う事で、適宜管理方法の修正
- 治療自体の効果を予測する材料
半固形化栄養剤
逆流の対策として期待されているが、エビデンスレベルの高い報告は私の知る限り無い
10,000PaS以上だと逆流が減ったとの報告もあるため、粘度がキー
個人的には下痢対策としてよく使うけれども、逆流対策ではあんまり
AST/ALT
肝炎等の肝細胞障害で上昇するため、肝障害の指標によく用いられる
栄養ではPNなど急速に栄養投与を行うと上昇することがある。低栄養が改善する時はALT優位で両者が低下
また過負荷でも上昇
成人におけるカリウム不可避損失量の推定値として、合計9.35mg/日とする報告、15.64mgとする報告がある。
また、便・汗・尿からも喪失があり、カリウムの体内貯蔵も必要なので1,600mg/日程度が平衡維持量と考えられる
胃瘻、身体の外側
【ボタン】:目立たない、邪魔にならない、ご抜去のリスクが低い、栄養の接続チューブが必要
【tube】:目立つ、邪魔になる、ご抜去のリスクが高い、経腸栄養の投与が容易
体の内側(胃内)でさらにバルーン、とバンパーに分類される
豆乳は牛乳の代わりになるか
時々聞かれるが、豆乳が代わりになるかどうか。タンパク質の量は大きな差が無い
が、カルシウムが結構違う
・牛乳→110mg/100g中
・豆乳→15mg/100g中
しかし、Caが指導内容の主題に関わらなければお知らせは不要か…
バルーン拡張術後の食事
バルーン拡張術とは、内視鏡を狭窄部まで挿入し、内視鏡で見ながらバルーン(風船)のついた拡張機器ををふくらませることによって狭窄部を広げる方法
少し調べたけど、消化管バルーン拡張術後の食形態は決まっていない。狭窄前の形態で良い
栄養の指標:コリンエステラーゼ(ChE)
肝でのタンパク質代謝能の指標とされ、低栄養では低値をしめし、脂肪肝や栄養過多では高値を示す
測定法が多く、基準値は施設により異なる。肝硬変や低栄養で低値、半減期11日もALBよりやや短い
PNI(Prognostic Nutritional Index)
複数の栄養指標を組み合わせて、外科手術を受ける患者の手術危険度や予後を推定する式が考案されている
日本では胃がん、食道がんなどを対象とした栄養指標として小野寺式が有名。アルブミンと総リンパ球数を使う
経腸栄養時の腹部膨満
★候補
・ガス:腸内フローラ異常など
・腹水
・消化管内容:イレウス、注入速度等
・腫瘤など
・血液:腹腔内出血など
・脂肪:肥満など
・尿:尿閉など
★化膿性脊椎炎
脊椎が細菌に感染した状態で、脊髄神経を圧迫したり刺激して様々な症状を引き起こす
治療は抗菌薬を使う。時には数か月間かかる事も
専門の栄養療法は私が探した限り無い。姿勢の制限がある場合は、食形態で対応が必要。食事場面を観察
経腸栄養中の嘔吐原因
■消化管の異常
- 胃癌
- 腸閉塞
- イレウス
- 腸重積
- 鼠径ヘルニア
- 腹壁瘢痕ヘルニア
- 大腿ヘルニア
- 胃・十二指腸潰瘍
- 胃食道逆流(食道裂孔ヘルニア、下部食道括約筋機能低下)
意識があれば、吐気を確認できるが…
リフィーディング症候群
一般的には飢餓状態にある低栄養患者が急に栄養を摂取して水・電解質異常を起こし、心停止を含む合併症を起こす病態
ハイリスクの代表的な疾患は、神経性食欲不信だけでなく、頸部悪性腫瘍等のがんに伴う低栄養なども含まれる
食事摂取基準2020、カリウムの耐容上限量は設定なし。
腎機能が正常で、カリウムのサプリなどを使用していない限りは、過剰のリスクは低いと考えられているためである
尿から排泄されますからね
PPNの主な適応
- ある程度の経口摂取ができるが、不足している場合の栄養補給
- 栄養状態が比較的良好で短期間の経口摂取不能
- 中心静脈カテーテル留置が危険
- 水分制限がない
- その他(TPN離脱期など)
refeeding.synのハイリスク
- BMI13以下、%BMI<2%、1週間の体重減少>1.0kg、
- 紫斑
- 血圧<80/50、起立時血圧低下、心拍数<40、QT延長
- 筋力:しゃがんだor寝た状態から立ち上がれない
- 体温<34.5℃
- 採血:K<2.5、Na<130、PO4<0.5mmol/L
水溶性食物繊維
食物繊維は人体が分解して利用できません。水溶性と不溶性がある
水溶性食物繊維は腸内細菌への作用が有名ですが、胃内容の粘調度を増して胃排泄を遅らせる働きがあります
血液検査の換算:リン
基準は
・2.2~4.1 mg/dL
・0.71~1.32 mmol/L
・換算係数は0.3229
論文上だと、普段使わないmmol表記なので困惑
血糖値も換算しないといけない場合が多いですよね。
果物のアレルギー
のどに違和感、のような口の中に限定して症状が起こるものは口腔アレルギー症候群という
アレルギーと思われていない事も。アレルギーの特徴である免疫反応が起こっている事が分かっているようです。加熱品は大丈夫な事もあり
血液中のカルシウム濃度
比較的狭い範囲、8.5〜10.4mg/dlに保たれており、濃度が低下すると副甲状腺ホルモンの分泌が増加して主に骨からカルシウムが溶け出して元の濃度に戻る
副甲状腺が高い状態が続くと溶け出す量が大きくなり骨粗鬆症へ
早期経腸栄養の理論的背景
絶飲食により腸管絨毛が萎縮して腸管関連リンパ組織(GALT)の機能が損なわれる、パイエル板におけるIgAの産生能やリンパ球の細胞障害性の活性が低下する
便秘
原因のひとつとして、消化管運動を調節する神経細胞の数の減少や機能低下がある、
また排便反射は、基本的に直腸に便が存在する、直腸内圧が上昇する、というシグナルで始まる。
脳梗塞などでこのシグナルが認識されず排便が起こせない場合がある
高Ca血症
よくみられるのは副甲状腺機能亢進症と癌。
癌ではPTH低値、PTHrP高値となる悪性体液性高Ca血症、と骨転移に伴うのがある
・軽度の場合は無症状.血清Ca値が、12~13mg/dl以上で倦怠感、疲労感、食欲不振などが起こる
つづく