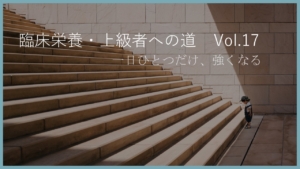病院で働きだして業務に慣れた。養成校時代の教科書では物足りなくなってきた病院栄養士向けの記事です
この記事は私がTwitterで発信している「1日ひとつだけ強くなる」をまとめました。 【476日~500日目】
下痢対応
薬の添付文書をもとに下痢を考えると、ほとんどの薬剤が原因候補に挙がってしまう。そこで、ソルビトール含有薬剤・消化管運動促進剤・下剤・広域の抗菌薬(カルバペネム系など)が入ってないか程度はチェック
上記以上となると薬剤師さんと協議
術後回復促進策における推奨事項
✓飲食し、動く
・管類を早く取り去る
・十分に痛みをとる
・気持ち悪さをとる
・プログラムを見直す
単に早く食べる飲むだけじゃなく、包括的な介入の中に栄養の項目があると認識して働きたい
ストレス(術後)の後に消化管の蠕動運動が回復するまでの期間
- 小腸4〜8時間
- 胃24〜48時間
- 大腸28〜72時間
膵頭十二指腸切除後の胃排出遅延対策
広く認められた栄養戦略はありません。長期間のDGE患者では、強制栄養を検討する必要がある
静脈栄養より経腸栄養が優先され、経腸栄養は吻合部を超えて栄養tubeの先端を留置する必要がある
待機的結腸手術の栄養 ※一部
- 栄養評価にて低栄養症例には栄養サポート
- 早期経腸栄養やonsのサポート
- 通常の術後は通常食の摂取推奨
- 免疫強化栄養は開腹結腸切除
食欲低下の原因検討
■環境要因
- 嗜好
- 甘い品が苦手
- しょっぱい味付けが好き
- 食形態
- 軟食が苦手
- 大量の輸液
- 病室の問題
- 電子音が四六時中なっている
- 同室者
- 窓やテレビが無い
経管栄養チューブ閉塞対策
- 定期的なフラッシング
- 半消化態栄養剤は閉塞を起こしやすい
- 最近汚染によるタンパク質のカード化が閉塞の原因
- 成分栄養、消化態栄養剤はカード化を生じない
- 十分なフラッシュと酢水ロック
- etc
食事摂取不良の原因検討
- 消化器症状があるか
- 嘔気嘔吐
- 腹痛
- 下痢、便秘
- 黒色便、潜血便
- 消化器疾患があるか
- 逆食、胃炎、胃潰瘍など
- 消化器に対する手術の既往があるか
- ダンピング症候群があるか
- 短腸症候群があるか
手術前は禁酒
アルコール乱用者において、周術期の合併症が2〜3倍に増加する事が報告されている。
出血量の増加、創傷治癒遅延、心血管系の合併症などが増加する事が報告されている
術前1ヶ月の禁酒によって臓器が回復するらしい
亜鉛の恒常性は、亜鉛トランスポーターによる細胞内外への輸送とメタロチネインによる貯蔵によって維持される
腸管吸収率は亜鉛の摂取量によって変動する。フィチン酸は吸収を阻害する。
術前栄養療法に必要な期間
- 生理機能を回復させるには4〜7日
- 体たんぱく質の回復を目標とした場合は7〜14日
化学療法を施行せず、手術を遅らせても問題ない場合は2週間となる
術後の段階食
米を主食としているアジアで流動、三分、五分、7分、全粥、米飯を、しているのは日本だけ
世界では4ステップが多い
イングランドでは段階の概念がなく、すぐにサンドイッチといった感じてかなり差があるよう
おそらく治療戦略も違う
化学療法中(オキサリプラチン)の食思不振にアイスや素麺は注意が必要
末梢神経症状、咽頭喉頭感覚異常は、冷たいものへの曝露により誘発又は悪化すること(以下略)
添付文書より
と、薬剤の添付文書に記載がある。普段接する栄養士は添付文書を見といていいかも
術前に液体を摂取するメリット
- 口渇感の軽減
- 胃腸の動きを活発にして胃液の滞留を減少
- 液体飲料を摂取することで胃酸が希釈され誤嚥性肺炎の重症化を防ぐ
術前の飲料は「clear fluids」で、清澄水のことですね
亜鉛の排泄
尿中排泄は少なく、腸管粘膜の脱落、膵液や胆汁の分泌に伴う糞便への排泄、発汗と皮膚の脱落、精液・月経血が主なものになる
排泄のメインは便ですね
胃排出速度の遅延があることを考慮すべき患者
- 糖尿病の罹患期間が10年以上
- 血糖コントロール不良
- 自律神経の障害を合併
糖尿病患者は固形では遅延があるものの、飲料は健常人と大きな差はないとされている
主な高カロリー輸液キット製剤
- ハイカリック
- ピーエヌツイン
- フルカリック
- エルネオパNF
- ワンパル
- ミキシッド
ハイカリックはアミノ酸、vit、微量元素を入れる必要があるなど、違いがあるので注意。
このキット製剤さえ投与されれば安心というのは無い
飲料の組成が胃排出に与える影響
- 容量:熱量が少ない飲料であれば、600mlまでは摂取量に比例して排出
- 熱量
- 浸透圧:285±5mOsm/lより高いと排出速度低下
- ph
- その他:温度に関しては議論が分かれる。炭酸含有は影響なし
亜鉛
日本では男性8.8、女性7.3mg/日で、通常の食品で過剰摂取が起きる事はほとんどない
大量亜鉛の継続摂取は銅・鉄の吸収障害による貧血などがある
サプリによる過剰に注意、耐用上限量は男性75歳以上だと40mg/日
本文を読むと体重によって変わりそう
経口補水液の浸透圧(mOsm/L)
- ソリタT顆粒2号 254
- OS-1 270
- アクアサポート 252
- アクアライトORS 200
- ソリタT顆粒3号 204
- アクアソリタ 175
ソリタの顆粒があることを初めて知りました。これが本当の飲む点滴ですね
術後のせん妄
術後に錯乱、幻覚、妄想状態をおこし、1週間前後続いて次第に落ち着いていく病態
抗精神病薬や睡眠薬など使用しつつ、1週間程度をしのげば落ち着いてくる。経口摂取も低下する
術後早期経口栄養が重要な理由
腸管内に栄養素が投与されない日が数日あると、腸管の物理的・免疫学的バリアの低下。呼吸器、肝、腹腔内の感染防御能の低下が示されているから
他にも理由はある
術後の早期経口摂取が勧められる理由
腸管蠕動運動を促すため。
手術侵襲により腸管血流の低下や神経内分泌により腸管蠕動は低下するが、経口摂取により亢進する。
エネルギー摂取が目的でないので、高エネルギーで無くても良い
手術後のENはPNより…
- 術後の代謝侵襲を抑える
- 胆汁鬱滞を回避
絶食と早期ENでは絶食の利点が無いと報告もある
胃排出を遅くする薬剤、次のような報告がある
- 水酸化アルミニウム(抗潰瘍)
- 硫酸アトロピン(抗コリン)
- ベータ刺激剤
- カルシウム拮抗剤
- ジフェニルヒダントイン
- ドパミン製剤
- etc
周術期実践マニュアルより
つづく