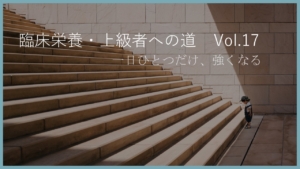病院で働きだして業務に慣れた。養成校時代の教科書では物足りなくなってきた3~4年目以降の栄養士向けの記事です。Vol.7
この記事は私がTwitterで発信している「1日ひとつだけ強くなる」をまとめました。
体系的ではありませんので、知らないトピックスがあれば、ご自身の学習を進める足がかりにしてただければ と思っています。1日目~はこちら
✔本記事の内容:臨床栄養のトピック25項目

酸塩基平衡のスクリーニング
血清Na-Cl>35で代謝性アルカローシス、Na-Cl<35でアニオンギャップ正常の代謝性アシドーシスの可能性
血液検査って数字だから一見簡単に思えるけど、変化で見るのが大切で、経験も必要
Naが低い≠塩を付加
重症病態の栄養
- 栄養障害が無ければ25〜30kcal/kgを最初の1週間で目指す
- タンパク質:1.2〜2.0g/kg
- 脂質:脂肪乳剤、経腸栄養はエネルギー比20〜40%(高炭酸ガスを伴えば比率を高く)
- 糖質:血糖180以下が目標、輸液は4mg/min/kg以下の投与速度
重症病態の経腸栄養
- 各種ガイドラインにおいて、静脈栄養より経腸栄養が優先されてる
- 早期経腸栄養で感染性合併症発生率が減る報告がある
- 腸が使えれば24h以内、遅くとも48h以内の経腸栄養投与開始を目指す
- ショック患者では腸管血流が低下しているため、NOMIに注意(この判定は相当困難)
COPD患者さんの栄養障害
原因は気流閉塞, 炎症性サイトカイン、年齢、喫煙や薬剤の影響,食事摂取量の減少や消化機能の低下、呼吸困難、社会的・心理的・遺伝的要因などが複合的に関与
まずは栄養評価、今までとこれからの見通しを立て栄養量を検討
COPDの低栄養リスク
全身性の炎症と呼吸障害により消費エネルギーが増加、筋タンパクの異化亢進によりサルコペニアになりやすい。
骨格筋減少は除脂肪量の低下を招き呼吸・運動機能が落ちる
ALBでの評価はかなり進行しないと数値が下がらないのでら、アテに出来ない
COPDの栄養評価
- 体重は独立した予後因子。体組成計も用いたい
- 体重(%IBW、BMI)、%AMC、%TSFなどの身体計測を重視
- %IBWが90%以下で栄養介入
- 身体計測の値は栄養投与に鋭敏に反応しないのが難点で、そこはL/Dの変化量を見てみる
アミノ酸入りのPPN
血管痛や静脈炎は末梢静脈投与時において遭遇することの最も多い合併症。比較的細い末梢血管に投与されるため、アミノ酸製剤は、浸透圧・pH.滴定酸度・温度などがそれら有害事象のリスク因子といわれている
安定期COPDの栄養状態
緩徐にマラスムス型の低栄養が進む事が多く、血清アルブミンは低値を示さない事が多いが、プレアルブミン、レチノール結合たんぱく、BCAAは低下する
あとは体格
COPDの栄養療法
■急性期
- エネルギー:REE×1.5-1.7kcal
- たんぱく質エネルギー比:15-20%
- 脂質エネルギー比:30-40%
■慢性期
- エネルギー:REE×1.3-1.5kcal
- たんぱく質エネルギー比:15-20%
- 脂質エネルギー比:25-30%
■肺性心合併で塩分7-8g以下
■その他は食事摂取基準
COPDの栄養
摂食時の息切れや腹部膨満感、咀嚼嚥下機能の低下などが減食につながる。
腹部膨満感がある場合はガスを発生しやすい食品を避ける。エネルギー密度の高い食事や分食を検討
n-3系多価不飽和脂肪酸を強化し、全身炎症対策
オキシーパは無い
栄養士が知っておきたい急性心不全の病態
- 肺静脈のうっ血
- 易疲労感、息切れ、呼吸困難
- 体静脈のうっ血
- 肝うっ血、下痢、腹部膨満感
- 心拍出量減少
- 虚血性腸炎、腎前性腎不全、etc…
暗記ではなく解剖から連動したい。症状によって栄養対応検討
うっ血性心不全の誘因として上気道炎、気管支炎などの呼吸器感染が重要。
食事では水・塩の過剰摂取が危険因子。最近では利尿薬が用いられ厳しい制限は強いられないが、それでも水・塩の制限は基本
塩を制限すると食事摂取量自体が減る事が多く悩ましい
心不全の栄養
高血圧、糖尿病、動脈硬化疾患、などが心不全の危険因子として挙げられている。
早期に栄養管理を行い、重篤な心不全を予防する事が重要
制限する栄養は評価によって適宜修正を行い、低栄養も考慮
ビタミンCの耐用上限量は食事摂取基準の表には無いが、大量摂取すると下痢を起こす。
なので、1g以上の摂取は勧められていない。
この性質を利用した下剤のモビプレップはビタミンCを約20g/1p配合。ニフレックには入っていない
ちなみに、食事摂取基準での成人における推奨量は100mg/日
経管栄養チューブの長さは120cm(商品によって違う?)胃内挿入だと55cm挿入。幽門後だと100cm以上になっている。これは体の中に入っているチューブの長さであり、体の外に残っている長さでは無い。
経腸栄養プランを立てる時にチェック
心不全の栄養管理
- 急性期
- 水:.5〜2.0L/日
- エネルギー:20〜25kcal/日
- 塩:4〜6/日
- タンパク質:1.0〜1.2/kg
- 慢性期
- 水:うっ血所見による
- エネルギー:25〜35kcal/日
- 塩:6g未満/日
- タンパク質:1.0〜1.2/kg
- 悪液質
- エネルギー:25〜35kcal/日
- 塩:6g未満/日
- タンパク質:1.2〜1.5/kg
低栄養が免疫低下となるメカニズム
エネルギーなどが不足する事により骨格筋が減少し,脂肪組織に置き換わる
骨格筋からのIL-15等が減少し、脂肪組織からの炎症性サイトカインが増加し慢性炎症が惹起、NK細胞の寿命を短縮させ,免疫能が低下
文献的には上記らしいです
心不全の輸液
水分投与量はNohria-Stevensonの分類と輸液に応じて、うっ血所見があればマイナスバランス。
経口摂取の場合には飲水制限が基本。経腸栄養の場合には濃縮タイプ(1.5〜2.0kcal/ml)を用いて水分制限を図る。
中心静脈栄養の輸液キット製剤は栄養を満たすと心不全患者にとっては水が多くなるため、使いにくい
心不全における塩分
ACCF/AHAガイドラインではステージ分類によって重症例て3g/日未満とされている。
日本の急性・慢性心不全ガイドラインでは6g/日未満の制限が推奨。
薄くしすぎると喰べられなくなるもんね
薄味≠減塩 でも無いですし
慢性期脳卒中の栄養
- エネルギー:25kcal/kg
- タンパク質:0.9〜1.1g/kg
- その他は食事摂取基準
- 嚥下機能評価
- 経口不良でEN
- 脳浮腫による悪心嘔吐、頭痛による摂取不良にはPN
- etc…
摂食嚥下障害と栄養
低栄養状態では、筋肉量の低下、疲労感などにより誤嚥を引き起こしやすい。経口摂取困難な場合は早期経腸栄養
誤嚥性肺炎だとして、食物誤嚥かどうか考える必要がある
怖いから取り敢えず経腸栄養は良くない。
侵襲でサードスペースへ水が移行している時が多い。血管内脱水を起こしている事も。
サードスペースから血管内に水が戻るリフィリング、循環内の血漿量が急に増えるので、血圧があがり、出血もしやすくなる。
ちなみにスペースは、細胞内がファースト、血管内がセカンド
腹水に減塩は有効か?
漏出液であり、合併症のない肝硬変腹水であれば有効。
塩分制限により10%の症例で負のNaバランスを保てる。利尿薬の投与節減などの報告もあり。しかし、過剰制限は食欲低下するので注意
血清ALB-腹水ALB でスクリーニング。1.1g/dl以上で漏出液、未満で滲出液を判別できる
食事摂取基準は道路のセンターライン
センターラインが何のために引かれているのか、どういう状況でまたいでも良いのかを理解するのが大切。
センターラインはひとつの数字だが、分布をあらわした結果なので、知っていると大外れはしない
褥瘡の評価と栄養
DESIGN-Rがあり、重症度と慢性の経過評価
炎症期→細胞増殖期→成熟期
の順に経過する
炎症期はエネルギー、タンパク質が不足しないよう栄養サポート。亜鉛銅鉄は増殖期へ。アルギニンは重症敗血症を伴う場合に使用中止考慮
つづく