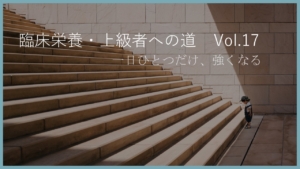この記事を書いている私は現役の病院栄養士ですが、知識の確認するために国試(臨床栄養の領域のみ)の過去問をチェックしました。 その4回目となります
栄養士の卵さんは勉強の足しに。 この記事を読んでおられる現役の栄養士さんは読み物として、気軽に読んで頂ければ幸いです。
✔本記事の内容
第33回管理栄養士国家試験の臨床栄養の分野のみ 5問
過去問は第33回管理栄養士国家試験を参照することにしました。厚生労働省のホームページからの印刷です。解答も同ホームページを参照しました。※厚労省のHPでは公開が終了しています
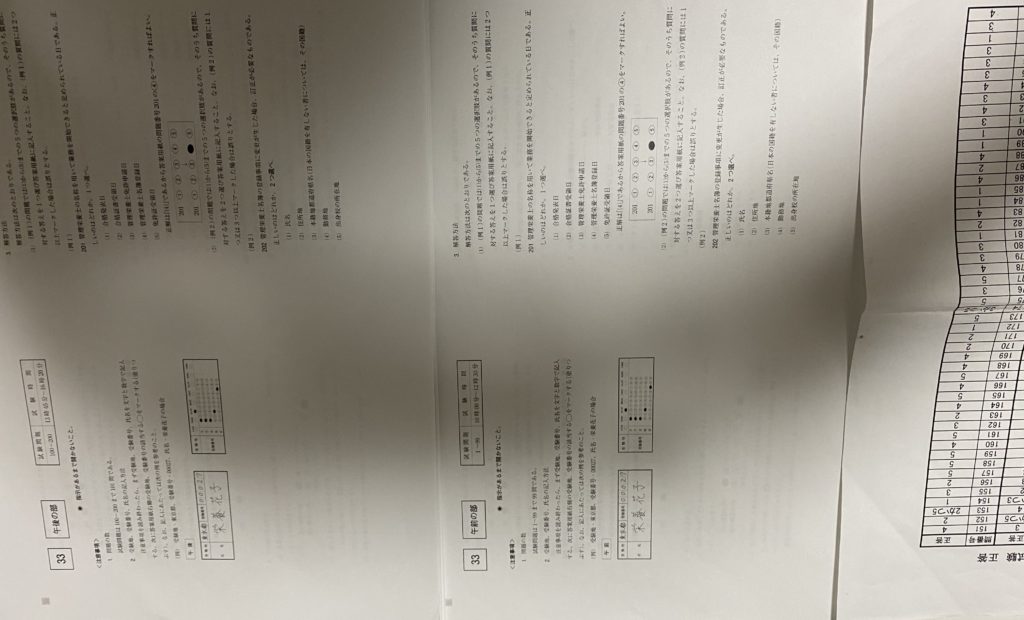
解説はこの記事を書いている都が実臨床の栄養士業務を意識して行いました
問題①(国試番号37)
肺炎に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- クリプトコッカスは、細菌性肺炎の原因となる
- 肺炎球菌は、非定型肺炎の原因となる
- 市中肺炎は、入院後48時間以降に発症した肺炎である。
- 院内肺炎は、日和見感染であることが多い
- 誤嚥性肺炎は、肺の上葉に後発する
解答
- ×
- ×
- ×
- 〇
- ×
解説
- × 細菌性肺炎というのは、その原因になる微生物が細菌であるという意味です。クリプトコッカスは真菌(カビ)なので真菌性の肺炎となります。微生物のおおざっぱな分類は下図

2.× 肺炎のタイプは定型と非定型があります。定型は、いかにも肺炎らしい肺炎のことで、発熱と痰の出る咳(湿性咳嗽)等がみられる状態。非定型は発熱はあるのですが、咳は乾いていて(痰がからまない)います。定型の肺炎の方が患者数は多いです。肺炎球菌は健康な人でも持っている菌で定形の肺炎によくなります
3.×
4.〇
肺炎を「誰に発生するか」で分類すると、院内肺炎と市中肺炎に分類できます。院内肺炎は「医療機関で発生」、市中肺炎は「一般社会で発生」です。
院内肺炎はケガや病気で入院している患者さんが発症します。体が弱り、感染症にかかりやすいため、感染力の弱い菌でも発症します。これを日和見感染といいます
一方、市中肺炎は健康な人がかかる肺炎ですので、感染力の強い菌で発症している事が多いです。
5.× 誤嚥性肺炎は唾や食物などの異物が気管から肺へ誤って入り、起こる肺炎です。物理的な異物で起こるので重力で異物が肺の下部へとどまり、そこで炎症を起こすので、肺の下葉・肺底などに炎症がみられます。設問の上葉とはは肺の上部(口側)。肺の解剖を確認しましょう
問題②(国試番号38)
骨に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ
- 骨の主な無機質成分は、炭酸カルシウムである
- 骨端軟骨は、骨端の関節面を覆う
- 骨への力学的負荷は、骨量を増加させる
- 骨芽細胞は骨吸収を行う
- ビスホスホネート薬は、骨吸収を促進する
解答
- ×
- ×
- 〇
- ×
- ×
解説
- × 骨の主な無機質成分は、リン酸カルシウムです。骨の形成で重要な栄養素はカルシウム・リン・ビタミンDですね
- × 骨端軟骨(こったんなんこつ)は、骨幹端と骨端の間にあります。骨端の関節面を覆っているのは関節軟骨。解剖の教科書でチェックしてください。
- 〇 骨を強くするのは、栄養だけではダメな理由で設問の通りです
- × 骨をつくる骨芽細胞(こつがさいぼう)と、骨を壊す破骨細胞(はこつさいぼう)の働きで骨は生まれ変わっています
- × ビスホスホネートは骨粗しょう症に使われる薬で、骨を壊す過程を抑える薬です。骨粗しょう症と合わせて学習しましょう。参考サイト:看護roo
問題③(国試番号39)
神経系の構造と機能に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 交感神経が興奮すると、消化管の運動は亢進する。
- 副交感神経が興奮すると、唾液の分泌は減少する
- 摂食中枢は延髄にある
- 三叉神経は、味覚の伝達に関与
- 味蕾は、味覚の受容器である
解答
- ×
- ×
- ×
- ×
- 〇
解説
- × 交感神経は人間のもともとの機能で獲物を狩ったり、肉食動物から逃げたりする際に活性化します。活性している時に消化管を動かす事に身体エネルギーを使う事は効率が悪いので亢進しない。前述の行動を起こしている時に必要な機能かどうかを考えれば異なる設問でも対応が可能。
- × 副交感神経は交感神経の反対、食事を含めたリラックスしている時に活性化します。食事時は食物を消化しないといけないので唾液の分泌は亢進しています。※唾液は交感神経が優位の時も分泌はされる
- × 摂食中枢は視床下部にあります。
- × 味覚の伝達は顔面神経。三叉神経は咀嚼や顔面の感覚を伝えます
- 〇 設問通り
神経系は全体像と、食事に関係する箇所が出題されやすい
問題④(国試番号40)
生殖器の構造と機能に関する記述である。正のはどれか。1つ選べ
- 卵巣は、卵胞刺激ホルモンを分泌する
- 子宮は、底部で膣と連続している
- 子宮内膜の増殖は、エストロゲンで促進させる
- 前立腺は内分泌腺である
- 精子は精嚢で作られる
解答
- ×
- ×
- 〇
- ×
- ×
解説
- × 卵巣は卵胞ホルモンを分泌しています。卵胞刺激ホルモンは下垂体から卵巣を刺激しています。
- × 構造を見ると、子宮底部・体部・頚部から膣へつながっています。構造をチェック。
- 〇
- × 内分泌腺とはホルモンをつくって分泌します。今わかっている範囲では、前立腺液を分泌していますがホルモンではないとされています
- × 精子は陰嚢のなかにある精巣で作られます。
問題⑤(国試番号41)
貧血に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ
- ビタミンB6欠乏は、巨赤芽球性貧血をきたす
- 銅の欠乏は、再生不良性貧血をきたす
- 溶血性貧血では、ハプトグロビン高値となる
- 腎性貧血では、エリスロポエチン高値となる
- 鉄欠乏性貧血では、不飽和鉄結合能(UIBC)高値となる
解答
- ×
- ×
- ×
- ×
- 〇
解説
- × 巨赤芽球性貧血の成因はビタミンB12と葉酸があります。赤血球の核は未成熟で、赤血球のサイズが大きくなるという病気です。核の合成成分にビタミンB12と葉酸が使われます。胃がビタミンB12を吸収する助けを行っているので、胃切除後に起きやすい。
- × 再生不良性貧血は造血幹細胞の異常によっておこる貧血です。銅が欠乏すると骨髄で正常に赤血球が作られなくなります。起こりやすいのは銅の摂取不足では無く、亜鉛の過剰摂取による銅不足からの貧血です。亜鉛は銅の吸収を阻害します。
- × ハプトグロビンは溶血の有無のチェック、肝障害の程度,などに使われます。溶血とは寿命前の赤血球がつぶれてしまう事です。原因が色々あります。
- × 腎性が分泌するエリスロポエチンというホルモンが骨髄に働いて赤血球の数が制御されていますが、腎臓の機能が下がってエリスロポエチンが少なくなり赤血球が少なくなって貧血になることが腎性の貧血です。なので、エリスルポエチンは低値になります
- 〇
文字同士の定式で暗記するのではなく、造血の全体像と貧血(赤血球)について、そこに関与する栄養素を図式で理解したいですね。
つづく