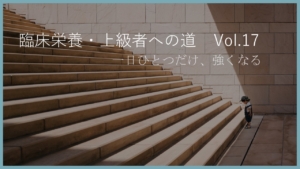病院で働きだして業務に慣れた。養成校時代の教科書では物足りなくなってきた3~4年目以降の栄養士向けの記事です。
この記事は私がTwitterで発信している「1日ひとつだけ強くなる」をまとめました。
体系的ではありませんので、知らないトピックスがあれば、ご自身の学習を進める足がかりにしていただければ と思っています。1日目(Vol.1)~はこちら
✔本記事の内容:臨床栄養のトピック25項目

食物繊維の摂取量は糖尿病の管理にどう影響するか
▶︎食物繊維は炭水化物摂取量とは無関係に20g/日以上の摂取を促す。
糖尿病のGLより。日本人の食事摂取基準より多いですね!
ただし過去の報告は食事由来ばかりで、粉末サプリでも良いかは不明
術後縫合不全に対する保存治療時の栄養管理
栄養療法と消化液分泌抑制剤や血液凝固第13因子の併用が有効な場合がある。
なかなか閉鎖しない時にNSTで第13因子を提案したら…知ってる感が。
まずは血液検査して、低値であれば薬剤補充
但し、GLの推奨レベルはCⅡ
食事摂取基準で栄養管理する期間
食事摂取基準は「1日当たり」で表現しているが、1食や1日の基準を示すものではない。
栄養の日間変動・健康被害を招くまでの期間が長期になる為。
実践・運用のテキストによると測定誤差・個人間誤差を容認して1ヶ月
ビタミンB1の必要量
ビタミンB1はエネルギー代謝に関与するので、0.45mg/1,000kcalが推定平均必要量として、その1.2倍が推奨量として食事摂取基準で定められている。
ちなみに、refeeding syndromeのときは200〜300mgが推奨。薬剤でのビタミンB1補充が必要
化学療法・PTX+AVA(パクタリキセル+ベバシズマブ)
手術不能または再発乳がんに対して施行される。
- 白血球減少85%
- 好中球減少75%
- 高血圧44%
- 蛋白尿59%
- etc
タンパク質制限は恐らく必要なし。腎機能はチェック。食事不振があれば栄養介入
小〜中等量の腹水に対しては、第一選択としてスピロノラクトンが投与される。
効果不十分時にはフロセミドが併用される。
この時点では恐らく入院はされていない。治療フローによると食塩制限は不応例や大量腹水に対して
虫垂炎の保存加療
穿孔してない虫垂炎は保存的にみる事がある
この間は絶食・抗菌薬が治療となるのがよくあるパターン。2〜3日で改善が無ければ手術へ
この待つ間の静脈栄養はビーフリード一択では無い気がする。ベースの栄養余力を評価。待てるかどうか…
レンビマ(レンバチニブ)
副作用発現率
- 食欲不振 48% 3日目〜
- 下痢 37% 2日目〜
- 悪心 14%
- 高血圧 49%
- 蛋白尿 45%
- 甲状腺機能低下 40%
食事調整は勿論、目標栄養量に満たしておらず、目処も立たなければ強制栄養検討を早めに
BCAA・vitDリッチなONS
- リハたいむゼリー
- リソースペムパルアクティブ
- メイバランスリハサポートmini
- メディミルプチロイシンプラス
- アミノケアゼリーロイシン40
BCAA含有量も大切だが、個人的には味が大切。特に飽きない。摂取はリハ後
亜鉛欠乏の貧血
亜鉛欠乏により赤芽球の分化・増殖が障害され貧血に
特徴は,赤血球数が減少、正球性または小球性貧血で,血清総鉄結合能は低下
手持ちの教科書では貧血鑑別のアルゴリズムにこれが無く、栄養の教科書見ても亜鉛欠乏貧血の記載なし
腹水
治療不応例や大量腹水の場合は、入院の上、食塩制限(5〜7g/日)、内服追加投与、内服+フロセミド静注などが行われる。
高度低ALBにはアルブミン製剤が投与。
食塩制限は全例には効果が無いので、モニタリング必須。
腎障害も併せてチェック
難治性腹水
腹水穿刺廃液、腹水ろ過濃縮再静注などが行われる。不応例にはシャントを考慮されるか、肝移植が検討される。
肝移植の周術期栄養は京大病院が積極的に研究されていて、免疫栄養や筋肉量の評価などを絡めたテーラーメイドな介入をされている
コレステロール
経口摂取されたコレステロールは体内で作られるコレステロールのおよそ1/3〜1/7
沢山摂取すると体内合成が減り、経口が不足すると合成が亢進する。
このため、経口摂取したコレステロールが血清総TCにそのまま反映されるわけでは無い
食物繊維摂取量
明らかな閾値が存在していないと考えられている。
アメリカの食事摂取基準では、14g/1,000kcal(目安量)
日本成人では大雑把に言うと、男性21g以上、女性18g以上。サンファイバー4包!
但し、動物実験では多量摂取で悪影響も
アルコール
アルコール(エタノール)は、ヒトにとって必須の栄養素ではない。
食事摂取基準では、過剰摂取による健康被害への注意喚起を行えにとどめ、指標は算定されていない
経腸栄養の排便モニタ
回数、量、性状、時間帯(タイミング)
水様便≠下痢
水様便は回数が減ってきてたり、医療上の問題が無ければ様子を見るのもアリ。
アルコール
195カ国のデータを統合したメタアナリシスは、飲酒が関連するあらゆる健康被害被害を総合的に考慮すると、アルコールとして10g/日を超えるアルコール摂取は健康障害のリスクであり、10g未満であってもリスクが下がるわけではないと報告
呼吸リハに関するステートメントに栄養療法の項目あり
- 栄養評価
- 低栄養の原因
- 栄養と運動の併用の重要性
- 機能的栄養素
- 嚥下障害
上記5項目について触れられています。栄養評価に骨塩量が挙げられてました
エネルギー産生栄養素バランス
目標となるエネルギー量が決まったら、食事摂取基準では、タンパク質を初めに定め、次に脂質、残りを炭水化物とするのが適切とされる
タンパク質には必要量があり、推奨量の摂取が勧められるため。
詳細は食事摂取基準を
下痢で経腸栄養を止める(腸管安静を選択)理由
- 下痢で脱水になる
- 下痢で電解質異常
- 皮膚のただれ(軟膏を塗っても治らない)
- 本人の不快感が強い
- アセスメントの結果が難治性の下痢
腸管を使った方が良いとはいえ、盲目的に継続も良くない
食物繊維のエネルギーは0〜2kcal/gと考えられている。
ちな、炭水化物に占める食物繊維は5%程度
食物繊維ベースのとろみ剤の食品成分を見たら結構エネルギーが書いてあったので、業者に問い合わせたところ、ほとんど吸収されないとの回答。製品によるのかも
ビタミンA
ビタミンAの摂取が不足しても、肝臓のビタミンA貯蔵量が20μg/g以下に低下するまで血漿レチノール濃度の低下は認められない。
なので、血漿レチノール濃度はビタミンA体内貯蔵量の判定指標としては不適切
わが国では同時化学放射線療法において60Gy/30回/6~8週程度の照射が標準的
根治照射には,少なくとも通常分割法で50 Gy/25回/5週以上に相当する線量が必要
放射線食道炎はほぼ必発。酸味・刺激物禁・軟菜などで対応。食事調整で対応が無理なら早めの強制栄養対応。
乳糜の組成
- 脂質0.4~6g/dL
- 総コレステ65~220mg/dL
- 総蛋白質 2.21~6g/dL
- ALB 1.2~4.1g/dL
- グロブリン 1.1~3.6g/dL
- GLU 48~200g/dL
- Na 104~108 mEq/L
- K 3.8~5.0 mEq/L
- CI 85~130mEq/L
- Ca 3.4~6.0 mEq/L
- P 0.8~4.2mEq/L
乳糜漏の脂肪制限
リンパ液が漏出している状態で、自然閉鎖を促すのに、腸管からの脂質をどの程度に許容するかは検証された根拠は見当たらない
尚、無脂肪にすれば、必須脂肪酸欠乏とvit類の欠乏リスクを負う事
つづく