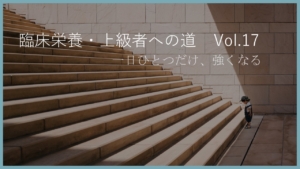病院で働きだして業務に慣れた。養成校時代の教科書では物足りなくなってきた3~4年目以降の栄養士向けの記事です
この記事は私がTwitterで発信している「1日ひとつだけ強くなる」をまとめました。
体系的ではありませんので、知らないトピックスがあれば、ご自身の学習を進める足がかりにしていただければ と思っています。1日目(Vol.1)~はこちら
✔本記事の内容:臨床栄養のトピック25項目
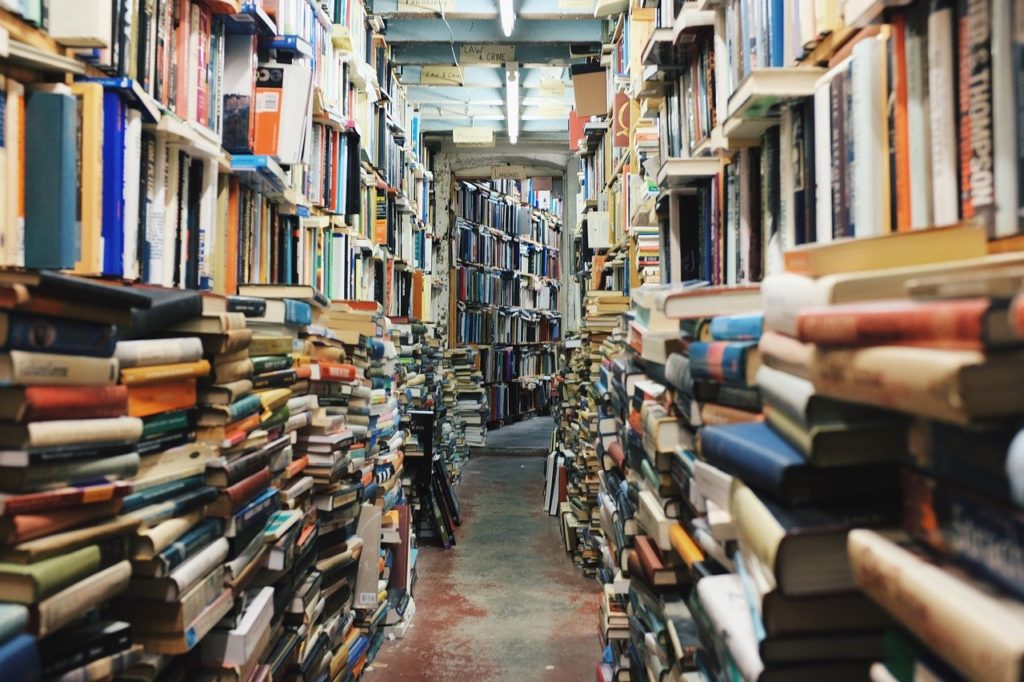
口の機能低下に対する食事4分類
1.器質性咀嚼障害
2. 巧緻性低下による運動障害性咀嚼障害
3.サルコペニアによる運動障害性咀嚼障害
4.器質性と運動障害性が併存
1.は歯の欠損や義歯の不適合など。2.は舌や頬の運動の巧緻性低下、3は筋力低下となる
必須脂肪酸欠乏による主な障害
■n6系
・魚鱗癬状皮膚症状
・血小板減少
・異常心電図
・創傷治癒遅延
・脂肪肝
■n3系
・知覚麻痺
・知覚異常
・倦怠感
・歩行不能
脂肪乳剤を含まないTPNでは数週間で発症と言われている
膵頭十二指腸切除術の術前5日間の免疫賦活栄養療法では、PD術後の感染性合併症を減らす。
報告では、創感染と腹腔内膿瘍、claien-dindo(術後合併症指標)が通常と比べ減少
細胞性免疫の指標「con A/PHA刺激リンパ球幼若化能」が高い
酸素化が悪い
①酸素の投与量をアップ
②酸素需要量の低下→安静にする等
酸素投与量がアップしている状況での栄養と食事
■マスクを外すとSpO2が低下する→経口不可・EN or/and PN
■ギャッジアップでSpO2が低下する→臥位で経口摂取検討、EN or/and PN
内視鏡で腸炎を見たら
普段の大腸内は血管透過性があるので、腸の壁に血管が見えている。これが結構きれい。
しかし、腸炎の時は白っぽくなってズルズルに
腸炎の時は腸管安静が治療方針に上がるので、食事内容は検討。ブレーキも踏めるよう
重症急性膵炎から慢性膵炎の移行
移行する症例は約22%とされている
慢性膵炎への移行に膵炎重症度や成因が関与すると考えられている。(急性膵炎GL2015年より)
急性膵炎がおさまり慢性膵炎へ移行している場合は、そこで栄養介入を終了せず、退院後の栄養指導を行う
タンパク質が「不耐性」である肝硬変患者では、適切なタンパク質摂取を促進するために、植物性タンパク質またはBCAA(0.25 g/kg/日)を経口経路で使用する必要があります。(推奨59、グレードB、コンセンサス89%)
ESPEN practical guidelineより一部
骨格筋のアンモニア処理機構
尿素回路以外のアンモニア処理機構として、筋肉においてグルタミン酸が合成される過程でアンモニアが処理される。この過程では、BCAAが消費される
肝硬変では骨格筋が減少してアンモニアの処理能力がさらに低下
がん患者さんの消費エネルギーは増加すると習ったが、一律では無い様子
癌種とステージによって変化する。場合によっては消費エネルギーが落ちているケースもある。
熱量計が無いと、モニタリングをして、プランを修正していくしかないですかね
乳がん発症のリスク減少
過去の検討では牛乳・乳製器品と発症リスクはリスクを減少させる可能性を示唆、しかし、脂肪含有量の多い乳製品の摂取はリスクを高めるとする報告もある
ちなvitD、カルシム、共役リノレイン酸の関与が挙げられている。乳癌GLより
緑茶は日本およびアジアの一部で習慣的に飲まれており、アジア地域では乳がんの発症率が低い
メタアナリシスではリスク減少した報告と効果がない報告があり、結論付けられていない
乳がんガイドラインより
臨床でよく聞く消化管ホルモン
・ガストリン
・セクレチン
・コレシストキニン
・GLP-1
・ソマトスタチン
コレシストキニンは十二指腸に脂質か蛋白が流れ込むと、十二指腸のI細胞から分泌され胆嚢を収縮、また膵臓の消化酵素分泌を促進
酸素化不良の栄養管理
肺胞・間質・Hb・血流のいずれかが悪い状態
【例】間質で炎症は酸素が肺から間質を通れないので、酸素化不良。CO2は出ていきやすいので横ばい。例:間質性肺炎
【対応例】EPA、DHA、GLA(ガンマリノレン酸)、抗酸化vit
換気障害時の栄養管理(O2↓、CO2↑)
→細胞はATPを得るために、基質(糖質・たんぱく質・脂質)とO2を使い、CO2が出る。基質によってCO2が出る量が異なる。
脂質はCO2排出が他の基質に比べて少ないので、高脂質の栄養剤を考慮
栄養療法が化学療法の効果や副作用を改善するエビデンスは、確固たるものがあるわけではない
ESPEN、ASPENの栄養ガイドラインでもルーチンの栄養管理は推奨されていない
栄養障害が著しい場合に、静脈栄養が有効なことは、臨床上ではよく経験される
ESPENのGLで化学療法・放射線療法時のダイエットカウンセリングは推奨レベルが高い
・摂取熱量と蛋白質を維持改善する目的で、患者の必要栄養量と必要タンパク質を提示する
・小冊子を使って説明
・治療の副作用と、食事の取り方のアドバイスをする
肝硬変の就寝前間食(LES)
- 効果が出てると確立されているのは、BCAA含有のみ
- 報告されているアウトカムとしてはALB、予後、QOLなど
- 但し、LESの栄養組成は確立されていない
- 耐糖能異常への適応は要注意
肝硬変の栄養療法、ポイント
■エネルギー25〜35kcal/kg IBW/日
■蛋白質 1.0〜1.5g/kg/日(蛋白不耐症なし)
肥満が無い場合は、35kcal/kg(実体重)/日。分割・夜食が推奨。
蛋白は栄養障害が無い場合は1.2g/kg(実体重)と
肝硬変診療GL2020より
肝硬変の病態に影響する食習慣としてコーヒーの有用性が報告されている
日常的(1日2杯以上のコーヒーを追加摂取)が肝繊維化進展予防や肝発癌リスクを低下させることを報告されている
コーヒーは色々ありますねホント。
長期の禁酒はアルコール性肝硬変の予後や繊維化を改善
複数の報告でされている。
肝臓繊維化の軽度、高度の両群で改善した報告があり,効果の発現は1.5年程度の禁酒期間が必要とされている
栄養プランを立てるときに、まず水分の投与量を決める。エネルギーよりも過不足が鋭敏に反応することが理由
循環がうまくいっていない→各臓器に必要な「モノ」が運搬されていないという事である
・脱水
・溢水
必要な「モノ」の中で特に重要なのが酸素
肝性脳症への亜鉛製剤(肝硬変ガイドライン)
肝硬変ではしばしば亜鉛欠乏があるので、亜鉛製剤による補充を提案
過去の検討では、健康関連の生活の質・アンモニアの改善・肝性脳症の程度・child-pughスコアの改善などが報告されている
課題も残ってるようですが…
軽症膵炎後の開始食
経口摂取が出来る様になった時点で経口、むりなら経腸。Clear liquidの必要はない様子
低脂肪・流動・固形は定まっていない
形態や栄養組成の調整は、常食から遠ざかるほど在院日数が増える印象。低脂肪の方が良いと思っていましたが…
急性膵炎の脂質管理
静脈からの脂質投与は膵外分泌を刺激しないので有用
但し、投与中はTGをモニタリングして、320mg/dl以上の場合は減量、400mg/dlを超える場合は脂肪乳剤は控える事が推奨されている
ENではトライツ越え
慢性膵炎の栄養
栄養状態は画一的に捉えられず、腹痛発作時、間欠期か。代償期・以降期・非代償期か、アルコール性・突発性か、膵性糖尿病の有無などを確認。
脂肪摂取量については薬で膵酵素補充、ESPENのGLでは脂肪便が制御できない場合に脂肪制限
つづく