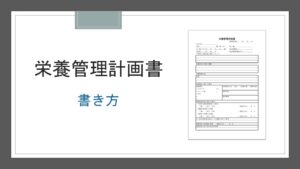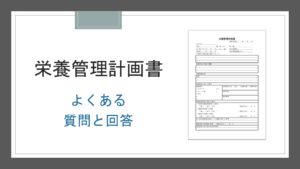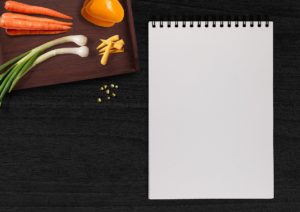栄養アセスメント項目についての解説は多いけど、実際の収集方法は教科書に載ってない・・・、良くしていきたいけど、みんなどうしているんだろう・・・
こんな 向上心はあるけど、困っている栄養士さん向けの記事です。
この記事を書いている私は、栄養士歴10年以上で今は病棟での栄養管理を主な業務としています。
✔本記事の内容
ベッドサイドでの栄養アセスメント法です ・準備・聞き取りまで ・聞き取り ・身体のアセスメント ・今後の計画 ・おわりに
ベッドサイドでの情報収集は医師・看護師・セラピスト向けの教科書は沢山ありますが、栄養士向けのはほとんどありません。困っている栄養士も多いと思いますので、まとめを試みます
準備・聞き取りまで

※この記事は看護師さんの入院初回情報収集が終わった後を想定しています
ベッドサイドに行く前の準備
電子カルテで欲しい情報を全て確認します。入院までの経緯、注意事項(言ってはいけない事など)、治療方針、提供している食事は必ず確認。どの項目を確認するかは経験を積むと自然と身に付きます
ベッドサイドで聞き取り前にすること
- 挨拶・自己紹介
- 本人確認
- 同意(これから栄養士が行う事の説明と所要時間)
- 環境確認(空間確保・騒音確認・照明・転倒転落防止など)
聞き取り
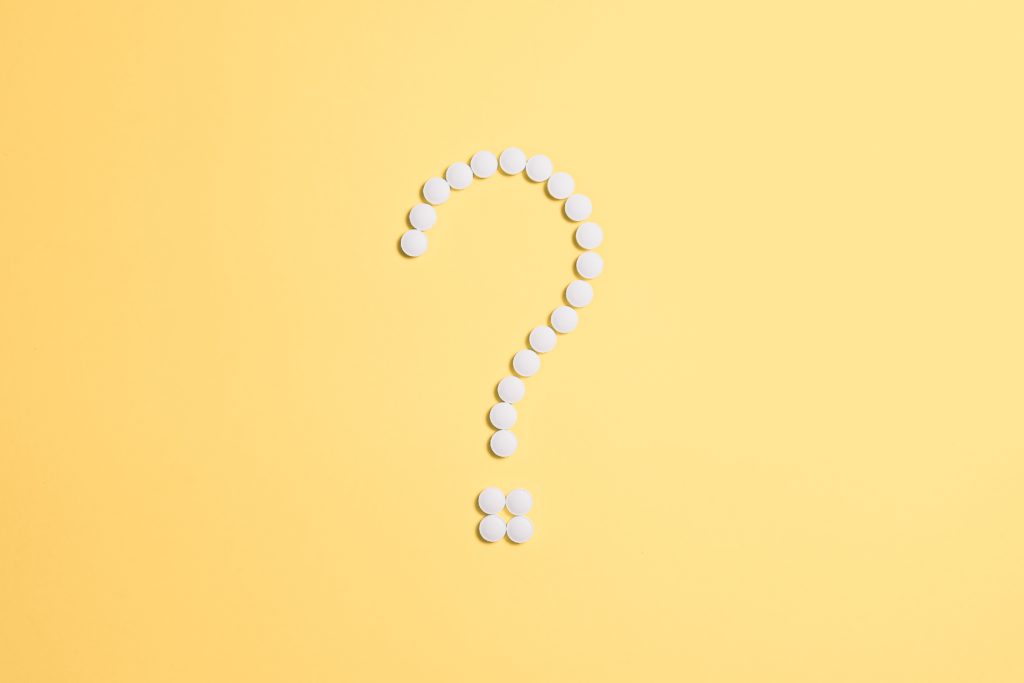
入院する前の栄養状態を把握する目的に行います。項目によっては入院直前、ここ2-3か月 を分けて確認したい。
入院前の食事内容を聴取
- 朝昼夕の食事量
- 間食・夜食
- 外食
- 飲み物
- サプリメント
- 病態に重要な栄養素(例:高血糖→糖質の量・頻度)
栄養指導と似ているが、聞き取った内容はあくまでも評価に使い、行動変容を促したりしない。
食事以外を聴取
- 現状の治療を患者さんの言葉で確認(理解・受け止め方の確認)
- 運動習慣
- 体重の推移
- 食欲の有無
病態や返答によって、生活歴をさらに深堀
- 専門用語は使わない
- 閉じた質問と開いた質問を使い分ける
- 誘導的な質問をしない
- 患者さんの理解・疲労に応じて立て続けに質問しない
- 傾聴する
慣れてきたら身体のアセスメントを行いながら問診が出来ると業務効率がup
聞き取りを行いながら手持ちのメモに情報を書き続ける栄養士さんを見かけます。気持ちは分かりますが、患者さんの目の前でのメモは控えめの方が好印象と個人的には思います。
身体のアセスメント

患者さんの体に触れるので、細心の注意を払います。もし”正常とは違う”を新たに発見したら、念のため他職種へ報告が必要です。
羞恥心への配慮(カーテンを閉める等)も忘れずに
みる
- 体格・体型
- 表情・意識・認知・言語機能など
- 姿勢・筋肉量
- 肌(色調・乾燥など)
- 口腔(ペンライトを用いて、歯の本数、舌、咬合力、乾燥、口蓋垂など)
可能な限り全身を。
聴く
聴診器を用いて、腹部・嚥下音を聴取。発声も確認
触れる
- 握手する(筋力の確認)
- 肩回り、上肢、下肢の筋肉量
- 腹部(膨満や痛みなど)※腹部聴診前
- 唾液の飲み込み(咽頭挙上、30秒間の嚥下回数)
- 病態に重要な部分(例:腎機能低下→浮腫の確認)
- 出来る範囲で上腕(下腿)周囲長(cm)、上腕皮下脂肪厚(mm)、体組成計
今後の計画

今まで得た情報をもとに、下記を患者さんへ説明します。シンプルな言葉を心がけましょう
- 大まかな治療の流れと、それにどう栄養サポートをのせるか
- 栄養の問題点と対応、見通し
- 患者さんからの質問があるか

おわりに
今まで示してきた情報収集を全ての患者さんに等しく行うことはお勧めできません。分かり切っている情報を取りに行くことは患者さんにも負担ですし、労力を無駄にすることになります。
準備段階から不要な項目を判断してカットしましょう
おしまい