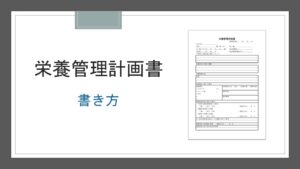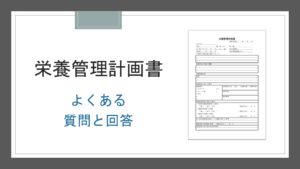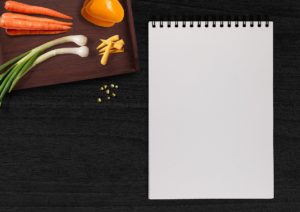「病院での栄養指導、学校での栄養指導実演をすることになったけど、何から手をつけて良いか分からない」こんな方向けの記事です。対象は栄養士の卵さん、病院栄養士1〜2年生です。
外来栄養指導を行うための準備知識をまとめました。
✔本記事の内容
- 栄養指導を行うための条件
- 実際の大まかな流れ
- 初回栄養指導でのチェック項目【実例】
この記事を書いている私は、栄養士歴15年程度。栄養指導は80~100件/月ぐらい行っています。
テクニックではなく、栄養指導開始までの全体像を知るための記事です
栄養指導を行うための条件

病院で行う栄養指導は診療報酬で成り立っています。診療報酬は医療機関が患者さんを診療・治療したときに受け取る報酬の事で、栄養指導もこれに含まれます。

診療報酬に定められている条件を満たさないと、上記が成立しないので、まずは栄養指導の対象となり、診療報酬を得るための条件を知る必要があります。
以下に示していきます
対象
- 特別食を必要とする患者※
- がん患者
- 摂食・嚥下機能の低下した患者
- 低栄養の患者
医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する食事。下記
- 腎臓食
- 胃潰瘍食
- 脂質異常症食
- フェニルケトン尿症食
- ガラクトース血症食
- 小児食物アレルギー食
- 肝臓食
- 貧血食
- 痛風食
- 楓糖尿症食
- 治療乳
- 特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
- 糖尿食
- 膵臓食
- てんかん食
- ホモシスチン尿症食
- 無菌食
医師からの指示
栄養指導は医師からの指示で行います。検査と同じですね。
医師からの管理栄養士への指導内容の指示は熱量・熱量構成・たんぱく質・脂質その他の栄養素の量・病態に応じた食事で具体的な指示を含まなければなりません
指導時間と得られる報酬
- 初回260点 おおむね30分以上
- 2回目以降200点 おおむね20分以上
1点=10円
記録
管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点及び指導時間を記載する必要があります。これは閲覧できるようにする必要があります
この記事で書いていない注意事項
概要を把握するための記事なので、省略しているのが下記です。
- 外来栄養指導の初回と2回目の間隔について
- 常勤である必要があるか
- 特別食の定義や詳細
- 嚥下調整食の詳細
- 低栄養状態の定義や詳細
診療報酬算定方法の留意事項(外部リンク:保医0305第1号)
制度上の縛りは以上です
実際の大まかな流れ

- 患者さんが来院・受付
- 検査・事前情報聴取など
- 医師の診察・栄養指導の指示
- 栄養指導の実施
- 栄養指導の次回予約
- 患者さんがお金を支払う
- 患者さんが病院から帰る
上が大まかな流れですが、実際は順番が入れ替わりもしますし、医師の診察の後日に栄養指導が予約される場合もあります。
飛び込みでいきなり当日予約が入る場合は、準備を迅速に行う必要がありますね。自施設のシステムを確認しておく必要があります
初回栄養指導でのチェック項目【実例】

初回栄養指導時に得たい情報を示します。急な予約以外は栄養指導前にカルテでチェックして下書きしておきたい所。
主たる情報
- 指導する内容:「対象」の項目で挙げた中から
- 指導対象:本人、妻など
- 指導に用いた媒体
主観情報(患者さんからの)
- 朝食、昼食、夕食
- 間食・夜食
- 塩分
- 外食
- 飲酒
- 喫煙
- 運動
- 職業
- 家族構成
- 調理担当
- その他(サプリの利用、嗜好、食欲など)
客観的な情報
- 体格
- 身体所見
- 検査
- 現病歴・既往歴
- 薬剤
得た情報からの評価
- 目標となる栄養量
- 摂取している栄養量
- 理解度
- プロブレムリスト
プロブレムリストに対して、実行度合いや優先事項を考慮して行動目標・精神的な目標などを具体的に立てていきます。各項目の解説を知りたい方はこちら
おしまい