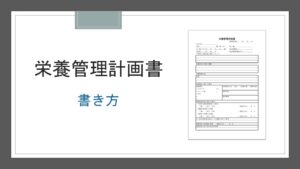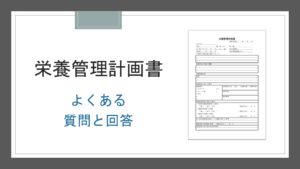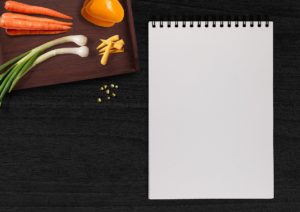昨日食べた食事の内容を聞き取って摂取エネルギーをしらべる方法を記事にしました。
この記事は栄養の専門職向けです
記事を書いている私は管理栄養士歴が15年以上、栄養指導や保健指導の経験があります。食事の内容を聞き取ってエネルギーを推定する方法はずっと実践してきました
この記事を読んで明日からすぐ出来るわけではありませんが、技術トレーニングを積めば出来るようになります。聞き取りながら電卓を叩いて計算すると、相談する側もプロに聞いてる感じがしますよ
トレーニングが必要な技術は以下の3点
- 食品交換表の暗記
- ポーションサイズ
- メジャーな食品のエネルギー
食品交換表を活用

料理は食品交換表で食品ごとに分解してエネルギーを推定します。
食品交換表とは、糖尿病の栄養療法で使われる本で、「糖尿病食事療法のための食品交換表 第7版
」が正式名です。大きな書店であれば置いてあります。
食品交換表では、1単位を80kcalと定めて、様々な食品において1単位が何gに当たるか示されています。ちょっと大変ですが、これを全部覚えます。単位が日常的に食べる量の倍数で設定されているので覚えやすいですよ
| 6枚切り食パン1枚(60g) | 2単位 | 160kcal |
| 卵1個(50g) | 1単位 | 80kcal |
| バナナ1本(100g) | 1単位 | 80kcal |
| さけ(中2/3切れ60g) | 1単位 | 80kcal |
| 牛乳コップ1杯(180ml) | 1.5単位 | 120kcal |
【例】パン・バナナ・卵を食べると…
6枚切り食パン1枚+卵1個+バナナ1本=320kcal
ポーションサイズを覚える

ポーションサイズはいわゆる「手ばかり」の事です
会話や身振り手振りで表現された食事量を重量(g)に変換する技術です
食品交換表の単位を暗記するだけでは聞き取った相談者さんの食事内容を推定できません。なぜなら、相談者側は「ほうれん草のお浸しを小鉢1つ分だけ食べた」と簡単に言えますが、食品の重量までは分からない事が多いからです
聞き取っているあなたが相談者さんの表現した食品量を確認して重量換算し、食品交換表の単位に変換します
【例】焼き魚の推定
相談者「鮭の切り身を1切れ、焼いて食べました」
=鮭80gと推定=交換表で1.5単位=120kcal
普段からのトレーニングとして、お浸しの青菜は40gでこれくらい、主菜の魚は80gでこれくらい… といった具合に食品の重量を体(眼や手)で覚える必要があります。厨房業務、盛り付け業務を行っていれば自然と身につくと思います。
加工食品のエネルギー

食品交換表に収載されておらず、よく食べられている加工食品はエネルギーを覚えちゃいます
【例】よく食べられる加工食品
| カップラーメン1個 | 350kcal |
| ハンバーガー1個 | 260kcal |
| ポテトチップス1袋(85g) | 480kcal |
幸い、普及している食品ほど、企業が栄養量を開示しているので調べやすいです。
自身がスーパーやコンビニへ行った時も小まめに栄養成分表示をチェックして日ごろからトレーニングをしましょう
こんな感じで計算する

食品交換表の暗記し、食品のポーションサイズを覚え、メジャーな加工食品を覚えたら聞き取りでエネルギーが推定できるようになります。以下に簡単な例を示します
栄養士「昨日食べた食事のカロリーを計算します、朝から順番に聞いていきますね。昨日の朝食は何を食べましたか」
相談者「パン1枚、卵ひとつ、牛乳を1杯です」
栄養士「パンは、食パンで6枚切りですか?」
相談者「そうです」
栄養士(6枚切り食パン1枚だから2単位だな・・・)
栄養士「卵はニワトリですよね、牛乳はこれくらいの(手で大きさを示しながら)コップ一杯ですか」
相談者「はい、その通りです」
栄養士(卵1個で1単位、牛乳は1.5単位、パン2単位と併せて朝食は360kcalだな・・・)
栄養士「昼食は何を食べましたか」
相談者「カップ麺を1個だけです」
栄養士「日清のカップヌードルですか」
相談者「はい、そうです」
栄養士(昼食は350kcalだな・・・)
栄養士「次は夕食です。昨日の夕食は何を食べましたか?」
相談者「夕食はなにも食べませんでした」
栄養士「分かりました。朝昼夕と食事を聞き取りましたが、他に口にされた食べ物はありますか?」
相談者「15時にポテトチップスを1袋たべました」
栄養士「ポテチはコンビニに置いてある普通のサイズですか?」
相談者「はい、そうです」
栄養士「分かりました」(ポテチ一袋で480kcalだな・・・、朝食360kcal、昼食350kcalだから・・・)
栄養士「あなたが昨日食べた食事のカロリーは1,190kcal/日です」電卓を叩きながら
相談者「それって多いんですか?」
~~以下相談がつづく~~
注意点
- 聞き取りの過少・過大申告、食品交換表の誤差、栄養士の評価など、誤差がおおく、絶対的なエネルギー量は算出されない
- 次回の聞き取り時に同様の推定を行い、変化をチェックすることが重要
- 算出するのは体に入る前の食事エネルギー。消化吸収率、消費エネルギー、病態変化などを考慮し、目的に応じて活用する
- この記事は科学的根拠に基づいていない
- 昨日の食事内容が習慣的な食事とは限らない
- 「推定されたエネルギーが少なすぎる!?」はよくある事で、体重変化などのモニタリングで栄養評価は総合的に行う
普遍的な方法では無いかもしれません。もっと良い方法があるかもしれません
つづく