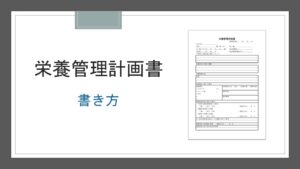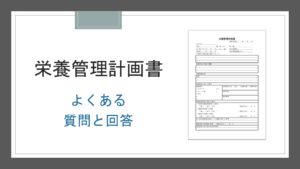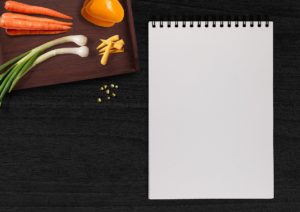「病院での栄養指導、学校での栄養指導実演をすることになったけど、どんな質問をしたらいいか分からない・・・」こんな方向けの記事です。対象は栄養士の卵さん、病院栄養士1〜2年生です。vol.2
今回の記事は2回目以降の外来栄養指導を想定し、テンプレ項目をSOAP形式でまとめました。
✔本記事の内容
- 開幕確認(前回からの変化、目標の確認)
- 客観的・主観的に確認が必要な重要項目
- 評価
- 計画
- 実際例
この記事を書いている私は、栄養士歴15年程度。栄養指導は80~100件/月ぐらい行っています
栄養指導のテクニックです。これから挙げる項目を押さえておけば、ある程度の栄養指導が出来ると思います
この記事は初回栄養指導の記事とセットです。先に読んで頂くことをオススメします

S:主観情報(患者さんからの)

S:開幕の確認項目
以下の2点をまず確認
生活が変わったか
前回の栄養指導から今回までの間に、何かイベントあったか、生活習慣が変わったかを確認。
結婚や職場の変更など様々。患者さんが関係ないと思っていても、栄養に影響があるかもしれません。それを踏まえて十分に聞き取ります
内容によっては、食事内容・間食など、これから示していく内容へ移行します
前回立てた目標が実行できたか
前回立てた目標が実行できたかを確認します。栄養士側から確認する前に患者さんから話はじめる場合もあるでしょう。形にとらわれずに進めていきたいところです。
行動変容のステージによっては実行できていなくても、とがめる必要は無いと思われます(来院はしているので無関心ではないと考えられる)
「怒りません・とがめません」のスタンスを栄養士が態度で示していれば正直に話しやすくなると思います。しかし、現状に良いか悪いかは伝える必要があります
実行できなかった場合の目標を修正するかどうかは、今後の聞き取り内容によって検討します
S:栄養に関わる重要項目
朝食、昼食、夕食
初回もしくは前回に確認した食事内容を再確認するフェーズです。
前回の指導記録をみながら、確認していきます。開幕に生活習慣の変化がないと返答された場合でも、「栄養量の確認で・・」など声掛けをしてから行います。確認すると以外と変化があったりします
間食・夜食
初回もしくは前回に確認した内容を再確認するフェーズです。
間食・夜食の減量が目標であった場合は、必ず確認。
果物を間食として食べる習慣がある方は季節の変化がありますよね。好きな果物が旬の時期だと摂取量も増えているかもしれません
外食
外食に関わる事目標であった場合は、必ず確認。
頻度の増減があれば、理由も確認。
気を付けないといけないのは外食≠悪という事です。外食の内容は把握して、目の前の患者さんに本当に不利益を与えているかは、客観指標を踏まえて考える必要があります
飲酒
飲酒に関わる事目標であった場合は、必ず確認。
アテも併せて確認です。ビールand日本酒なのか、ビールor日本酒なのか等、栄養士側が勘違いで過少見積もりをしていても、患者さん側は良しとしてそのままにするケースもあるので、具体的に再確認
飲酒量が増えているからといって、過剰にとがめると次回から隠したりしてしまうので、修正は慎重に
O:客観的な情報
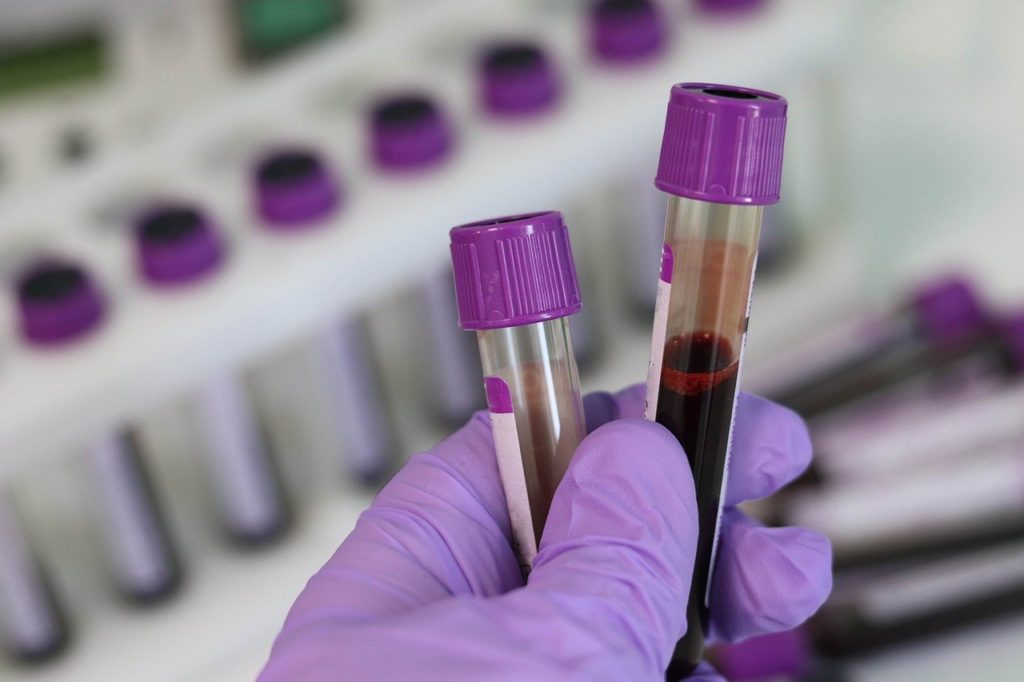
体格:体重・BMI
栄養指導する場所に体重計があれば、その場で測定。ご本人からの申告でもOKですね。
体重を確認してBMIを算出し、前回と比べてどうかを評価します。体格が目標に関わっていれば栄養士のコメントが必要ですね。
腹囲、上腕周囲長などもここの項目に含まれます
検査所見
血液検査だけではなく、血圧、画像などもここに含まれます。
主たる介入の評価項目がどう変化しているかは確認必須ですし(糖尿ならHbA1cなど)、患者さんと共有する必要がありますね
可能であれば、開幕に患者さん自身の感触を聞いてから、この項目を共有すると良いと思います。患者さん自身の感触と評価項目の変化が一致していればいいですね、一致していなければ共に考える必要があります。
又、前回からの推移を確認、変化があれば理由を検討する。注意点としては薬や運動量などみて、理由を栄養・食事だけにしない事
必要に応じて確認したい
塩分・喫煙・運動・家族構成・調理担当・職業・現病歴・既往歴・目標栄養量
A:得た情報からの評価

今まで得てきた情報で、下に挙げた項目を検討し、記録へ記載
摂取栄養量
聞き取った内容と体重変化を考慮して推定します。絶対量を正確に出すより、相対的な変化量を捉える事が重要。
電卓を叩きながら行うと、プロ感がでます(笑)
全体評価
前回評価したプロブレムリストの見直し、どうなったかを評価して、リストを変更し記録する。
前回立てた目標が実行出来ているか。実行困難かなのか、程度を変える(例:運動時間を減らす)かを検討する。
行動変容のステージを評価、ただし順調に階段を上がるばかりではない事を心得ておく
P:計画

プロブレムリストに対して、実行度合いや優先事項を考慮して行動目標・精神的な目標などを具体的に変更します。
行動変容ステージによっては、効果が少ないと考えられても患者さんが主体的に立てたら🆗。病態を評価し、順調であれば現状維持(増悪予防)でも良い。
立てた目標は必ず記録、次回の栄養指導時に必要です
実際例
栄養指導の記録と、今まで示した内容で指導した記録を並べておきます。初回→今回にあたっての変更箇所は青色にしておきます。参考にしてみてください
指導する内容:外来・糖尿病食
指導対象:本人のみ
指導媒体:献立表、間食のカロリー一覧
s)
朝食:6:00(仕事によって変化):菓子パン×2、コーヒー牛乳200ml
昼食:12:00 :コンビニ弁当×1(500~700kcal程度?)、おにぎり×2
夕食:20~22時(仕事によって変化):米飯200~250g 主菜(肉が多い)、飲酒
間食・夜食:昼食後から夕食までの間に菓子パンを1~2個摂取。夜食無し
塩分:塩辛が好きで2日に一回は摂取、間食でポテトチップスをたべる、昼食でカップ麺を摂取する事もある
外食:1~2回/週、牛丼屋、うどん屋。1人前の食事に何か1品追加して食べる
飲酒:350mlのビールを×1/日 休肝日無し
喫煙:なし
運動:なし。仕事のみ
職業:運送業務、積み荷をするため、運動量は多い
家族構成・調理担当:妻、子供2名(5歳・3歳)、調理担当夕食は妻、朝昼は自身
その他:サプリメント・健康食品の使用無し、シフトワーカーなので休日不定期、食欲は常にある。趣味は動画を見る事
O)
体格:身長170cm 体重80kg BMI27.6 IBW63kg。肥満体形
身体所見:下肢痺れなし、下肢に潰瘍など無し
検査:Glu(空腹時)200、Hba1c7.5、中性脂肪250、総コレステロール300、AST/ALT/γ-GDP、etc…(血液性化学検査を転載)
現病歴:糖尿病疑い
既往歴:2年前より高血圧
薬剤:〇〇(降圧剤)を毎日1錠
A)
目標となる栄養量:1900kcal 30kcal/kg(標準体重)
推定摂取栄養量:2000~2800kcal
理解度:良好、準備期
プロブレムリスト:#1過食、#2菓子パンの間食、#3飲酒量、#4・・・
P)
1.昼食と夕食の間は間食を1品だけにする
次回栄養指導時に間食の詳細な聞き取りを行う
指導する内容:外来・糖尿病食
指導対象:本人のみ
指導媒体:献立表、間食のカロリー一覧
s)
菓子パン、1個だけに我慢しました!やればできますね。数値も少し改善していると思います
朝食:6:00(仕事によって変化):菓子パン×2、コーヒー牛乳200ml
昼食:12:00 :コンビニ弁当×1(500~700kcal程度?)、おにぎり×2
夕食:20~22時(仕事によって変化):米飯200~250g 主菜(肉が多い)、飲酒
間食・夜食:昼食後から夕食までの間に菓子パンを1個までに減らした。休日はポテトチップスを1袋食べる、チョコやクッキーもあまり我慢せず食べる。夜食なし、
塩分:塩辛が好きで2日に一回は摂取、間食でポテトチップスをたべる、昼食でカップ麺を摂取する事もある
外食:1~2回/週、牛丼屋、うどん屋。1人前の食事に何か1品追加して食べる
飲酒:350mlのビールを×1/日 休肝日無し
喫煙:なし
運動:なし。仕事のみ
職業:運送業務、積み荷をするため、運動量は多い
家族構成・調理担当:妻、子供2名(5歳・3歳)、調理担当夕食は妻、朝昼は自身
その他:サプリメント・健康食品の使用無し、シフトワーカーなので休日不定期、食欲は常にある。趣味は動画を見る事
O)
体格:身長170cm 体重79kg(〇月〇日)←80kg(前回日時) BMI27.3 IBW63kg。肥満体形
身体所見:下肢痺れなし、下肢に潰瘍など無し
検査:Glu(空腹時)200、Hba1c7.3、中性脂肪240、総コレステロール300、AST/ALT/γ-GDP、etc…(血液性化学検査を転載)
現病歴:糖尿病疑い
既往歴:2年前より高血圧
薬剤:〇〇(降圧剤)を毎日1錠
A)
目標となる栄養量:1900kcal 30kcal/kg(標準体重)
推定摂取栄養量:2000~2800kcal
理解度:良好、準備期⇔実行期
プロブレムリスト:#1過食、#2菓子パンの間食、#3飲酒量、#4菓子パンと間食の認識不足 #5・・・
- 客観的な指標の悪化なし
- 間食量が多く、本人も摂取している量を把握できていない。前回指導の目標を「一品にする」としたが、菓子パンのみを1品にして、間食は継続摂取されている
- HbA1c・中性脂肪・体重はわずかに低下しているが、誤差範囲か。菓子パンは減らしているので継続し、まずは自身の間食量を一定に
P)
1.昼食と夕食の間は菓子パンを含め間食を1品だけにする
次回栄養指導時に間食の摂取量を再確認、運動量の介入も検討する
栄養指導の開始前に前回までの栄養指導記録を確認して、どんな指導をしてどんな目標を立てていたのかを確認しておくと指導がスムーズになります。これは業務の時間と相談しながらとなります。ただし、あらかじめシナリオを決めすぎて栄養士のやりたいことばかり押し付けないよう注意しましょう
おしまい