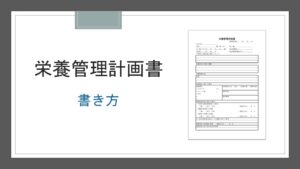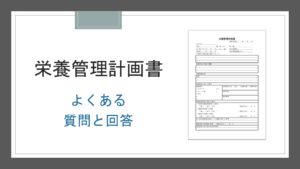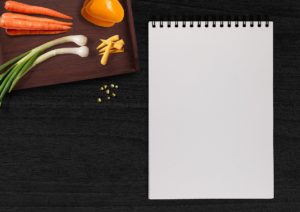患者さんの必要たんぱく質量の計算方法を知りたい。栄養アプリで計算されているが、手計算でも出来るようにして病棟でパパッと食事オーダーを決められるようになりたい
こんな悩みを抱えている、病院栄養士(医療者)向けの記事です。本記事では 食事オーダー時に悩ませる問題のひとつ、「必要たんぱく質量」についてまとめました
✔本記事の内容
必要タンパク質量の算出する手順 2ステップ
- 1⃣ 計算式に使う体重の決定
- 2⃣ 体重に乗じる定数の決定
必要たんぱく質量の算出式は 1⃣×2⃣=〇〇g/日です。順番に示していきます。
記事を書いている私は病院で働いています。私は病棟での栄養管理を中心に仕事をしていて、各種ガイドラインを読んでいますし、毎日患者さんの必要たんぱく質量を計算しています
この記事を読めば、急な問い合わせにも電卓片手に必要たんぱく質量が即答できるようになります。出来るようになると他の職種から重宝されます。ぜひご覧下さい
1⃣計算式に使う体重の決定方法

まず、必要たんぱく質量を算出したい患者さんの計算式に用いる体重(BW)を決めます。単位はkgで進めます。以下の2つのCHECKで決めます。 情報が無い、測定ができない場合は身長のみメジャーで測定。
※この段落は以前に公開した「必要エネルギー算出に必要な体重」の項目と同じです
- たまっている→ 普段の体重が候補。STEP2-1へ(UBWルート)
- たまっていない→ 今の体重が候補。STEP2-2へ(BWルート)
- 情報が無い or 体重を測定できない。STEP2-3へ(IBWルート)
- 患者の普段の体重(UBW)を聞き取り等で確認、BMIを算出。※ BMI=UBW(kg)/身長(m)/身長(m)
- 算出されたBMIが下記の表でどこに該当するかを確認、目線を右へ
- ABW・IBW・UBW・UBW+追加の中からどれを使うかが分かる
- 必要エネルギーの算出式に使う体重が決定される
| BMI | 計算式に使用する体重 |
| 30以上 | ABW 調整体重 :(BW-IBW)×0.25+IBW |
| 30未満25以上 | IBW 標準体重:身長(m)×身長(m)×22 |
| 25未満18.5以上 | UBW 確認した普段の体重をそのまま使う |
| 18.5未満16.1以上 | IBW 標準体重:身長(m)×身長(m)×22 |
| 16.1未満 | UBW+追加 普段の体重を確認、目指す必要エネルギー分を追加 |
- 患者の体重(BW)を聞き取り・測定等で確認、BMIを算出。※ BMI=BW(kg)/身長(m)/身長(m)
- 算出されたBMIが下記の表でどこに該当するかを確認、目線を右へ
- ABW・IBW・BW・UBW+追加の中からどれを使うかが分かる
- 必要エネルギーの算出式に使う体重が決定される
| BMI | 計算式に使用する体重 |
| 30以上 | ABW 調整体重 :(BW-IBW)×0.25+IBW |
| 30未満25以上 | IBW 標準体重:身長(m)×身長(m)×22 |
| 25未満18.5以上 | BW 今回測定した体重 |
| 18.5未満16.1以上 | IBW 標準体重:身長(m)×身長(m)×22 |
| 16.1未満 | BW+追加 現在の測定した体重に目指す必要分を追加 |
※このルートは体重不明・測定困難な場合
IBW (標準体重:身長m×身長m×22) を使用する事が決定。ただし、極端にやせてる場合はIBWより減らる(どれくらい減らすかは評価者の経験から)。
STEP❶~❷の手順で必要エネルギー計算式につかう体重が決まれば、次の項(体重に乗じる定数の決定)へ。
イメージとしては必要エネルギーを算出する患者さんの、水分を除いた目指すべき体重を決めています。
2⃣体重に乗じる定数の決定方法

体重が決まれば、次に乗じる定数を決めます。病態によって異なりますが、大体1.0g/kg/日前後です。 侵襲(ストレス)があれば多くなり、臓器障害(腎・肝)があれば少なくなる傾向です
一覧表は基本→病態別→肝疾患→腎疾患と分けて示しています
基本
| 最低必要量 | 0.6g/kg |
| 正常(侵襲なし) | 0.8~1.0g/kg |
| 高齢者・フレイルティ | 1.1~1.3g/kg |
| 上限量 | 2.0g/kg |
基本は活動量・ 必要エネルギーとの割合を考慮して設定するのが望ましい ですね
病態別
| 慢性膵炎 | 1.0~1.5g/kg |
| 急性膵炎 | 1.0~1.5g/kg |
| 潰瘍性大腸炎 非活動期 | 1.0~1.2g/kg |
| 潰瘍性大腸炎 活動期 | 1.5g/kg |
| クローン病 非活動期 | 1.0~1.2g/kg |
| クローン病 活動期 | 1.5g/kg |
| 短腸症候群 | 1.0~1.5g/kg |
| 担がん | 1.0~1.2g/kg |
| 周術期(手術内容考慮) | 1.2~2.0g/kg |
| 重症病態 | 1.2~2.0g/kg |
| COPD | エネルギー比15~20% |
| 急性心不全 | 1.0~1.2g/kg |
| 慢性心不全 | 1.0~1.2g/kg |
| 心不全 悪液質 | 1.2~1.5g/kg |
| 神経性食欲不振 | 1.0~1.5g/kg |
| 脳卒中 慢性期 | 0.9~1.1g/kg |
| 褥瘡(創部考慮) | 1.2~1.5g/kg |
肝疾患
| 慢性肝炎 安定期 | 1.2~1.5g/kg |
| 慢性肝炎(肥満)、脂肪肝 | 1.0~1.5g/kg |
| 肝硬変 たんぱく不耐症- | 1.0~1.5g/kg |
| 肝硬変 たんぱく不耐症+ | 0.5~0.7g/kg + BCAA製剤 |
| 急性肝炎 | 0.8~1.2g/kg |
| 劇症肝炎 極期 | 0g/kg |
肝疾患は病態によってはたんぱく質を制限する必要があります。又、アミノ・BCAA酸製剤(リーバクトやアミノレバン)の摂取も考慮する必要があります
腎疾患
| 糖尿病腎症 1期・2期 | エネルギー比20%以下 |
| 糖尿病腎症 3期 | 0.8~1.0/kg |
| 糖尿病腎症 4期 | 0.6~0.8g/kg |
| 急性腎障害(AKI)保存療法 | 0.6~1.0g/kg |
| 急性腎障害(AKI)透析 | 1.0~1.5g/kg |
| 急性腎障害(AKI)維持透析・異化亢進 | ~1.7g/kg |
| 慢性腎臓病(CKD)G1・G2 | 過剰を回避 |
| 慢性腎臓病(CKD)G3a | 0.8~1.0/kg |
| 慢性腎臓病(CKD)G3b | 0.6~0.8g/kg |
| 慢性腎臓病(CKD)G4・G5 | 0.6~0.8g/kg |
| 血液透析 | 0.9~1.2g/kg |
腎疾患病も病態によっては、たんぱく質を基本より少なくコントロールします。腎疾患のたんぱく質コントロールの目的は腎臓を守る事です。優先順位を考慮。
表は各種ガイドライン、教科書を基に作成しました。たんぱく質必要量から考えると相反する病態をいくつも抱えている場合があります。対応方法としては、 治療方針・病態を把握して優先順位を立ててからたんぱく質投与量を決めていきましょう
これで、計算が出来るようになったと思います。
必要たんぱく質量の算出式は 1⃣×2⃣=〇〇g/日 です
実際の計算例・補足
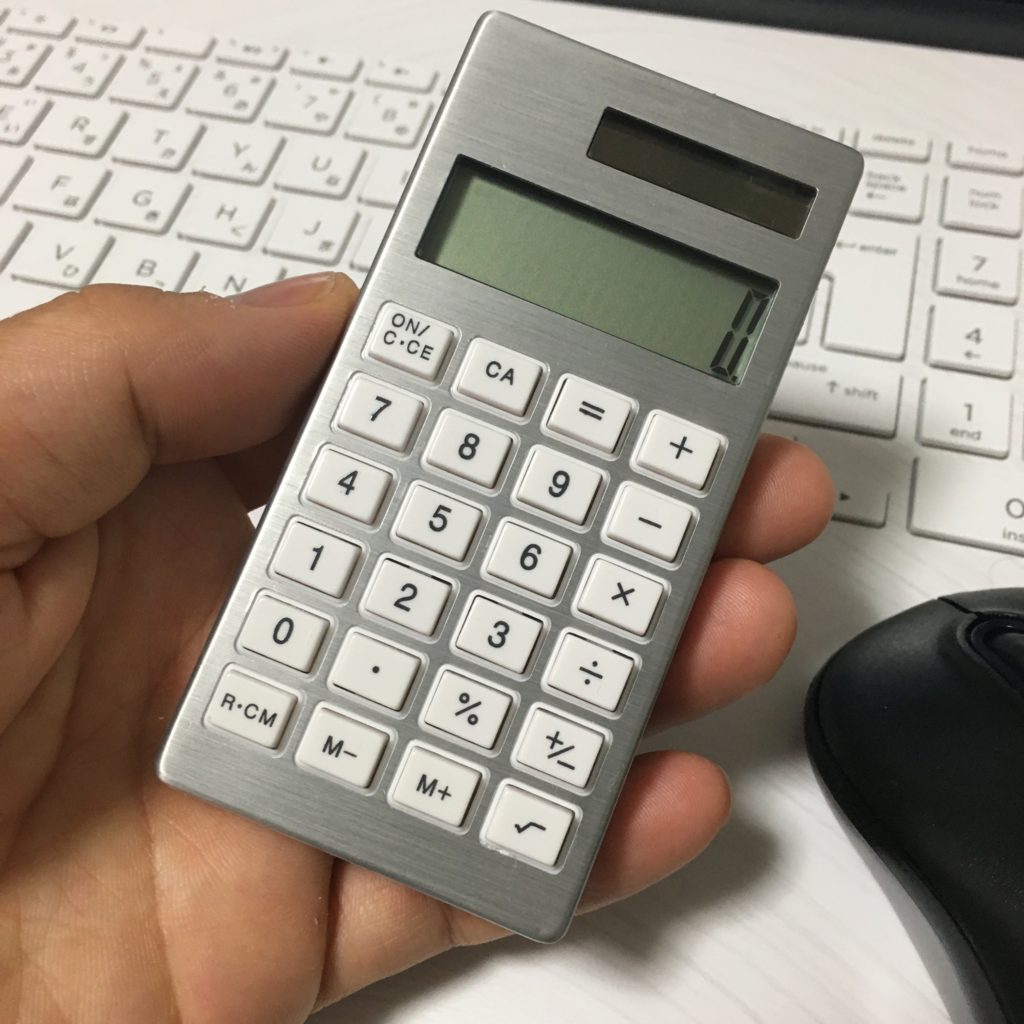
では、今まで考えてきた体重・定数をつかって計算例を示していきます
実際の計算例 入院時を想定
- 男性 80歳 身長170cm 体重50kg
- BMI 17.3(50÷1.7÷1.7) IBW63.5kg(1.7×1.7×22)
- 疾患:慢性腎障害(CKD G3a)、褥瘡(DESIGN-R®20)
- 入院の目的は遷延する褥瘡の改善。尿たんぱくは1+、尿中蛋白/クレアチニン比0.13
- 1⃣計算式に使う体重:体に水が溜まっていない事を確認(CHEK①)し、無かったのでBWルート(CHECK② -2 )へ。BMIは17.3なので「18.5未満16.1以上」に該当、IBWである63.5kgを計算に用いる事を決定
- 2⃣体重に乗じる定数:入院の目的が褥瘡治療であり、CKDのタンパク質制限も比較的ゆるくてもいけそうなので投与は多く設定したい、しかし計算式が標準体重を使用しているため、いったん慢性腎障害G3aの上限である1.0g/kgを採用
- 必要たんぱく質量の計算式:1⃣63.5×2⃣1.0→63.5g/日
以上で初期の必要たんぱく質量(目標)が決まりました。 最大量に設定して過剰の兆候があれば投与量を下げるのか、最小量にして徐々に最大まで上げるかは病態を考慮
補足
必要量を計算すると具体的な数値が出てくるので、守りたくなります。しかし、出てきた数値は科学的根拠としては弱く、 どれくらい体が栄養を吸収しているかは分からないため、モニタリングが重要となります。
- モニタリング:設定したタンパク質を投与開始してから、腎機能(BUN・尿蛋白・尿中蛋白/クレアチニン比等)をモニタリング、褥瘡の改善に乏しければ腎機能の悪化が無いかチェックしながらたんぱく質投与量を増やしていく。投与量が基準以上になるときには明確に主治医・共観医に伝達
- 四肢を切断された患者はどうするか?
-
下記の図から補正値を代入、推定式を用いて実体重(本来手足があった場合の)を算出

推定式:実体重=現体重×[1+補正値(%)÷100]
おわり