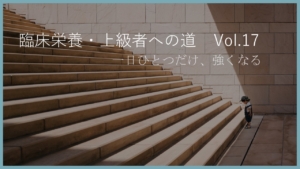栄養士として働いてはいるけど、大きな病院で栄養管理がしたい!。でも、正職員は競争率が高くライバルが多い。どんな準備したらいいのか・・・。こんな悩みを抱えている栄養士向けの記事です。
本記事では、総合病院、大きな病院の書類審査、筆記試験、面接対策に対する具体的なやるべき事を公開します。
- 履歴書のスペックを上げる
- ガイドラインと問題集のチェック
- 今の仕事を説明する力
記事を書いている私は病院で働いています。 転職活動中は1年で5カ所の病院を受けて、3カ所はパスしています。私の経験から有効だと考えられる方法をまとめました。お役に立てれば幸いです
書類審査:履歴書のスペック

タイトルで示している履歴書とは職務経歴書も含みます。
履歴書のスペックをアップさせます。スペックを上げるとは、履歴書の材料を作っておく事で、「情熱をもって仕事していました」などの抽象的な作文を頑張るのではありません。材料は職場での業務以外で作ります。
材料は資格、専門雑誌への記事掲載、学会発表です。順番に示していきます。
資格
- 病態栄養専門管理栄養士(と上位資格)
- NST専門療法士(と上位資格)
- 糖尿病療養指導士
上記が所持しておきたい病院栄養士での有力な資格です。
所持していると履歴書に書けるので、ある程度の経験があると採用側は判断できます。色々な資格がありますが、学会・栄養士会が認定している資格は評価が高いと思われます。
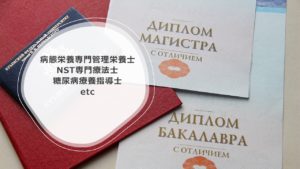
専門雑誌への記事掲載
難易度は高いですが、経験があると履歴書のスペックが高くなります。「病態栄養学会」「臨床栄養代謝学会」等の学術誌でも、「臨床栄養」「ニュートリションケア」などの商業誌でも良いと思います。
これらを履歴書に書けると強烈にスペックを上げる事が出来ます。日常的に行っている方はそもそも就職先に困っていないと思います。
学術誌への投稿は研究をして論文発表をすることです。商業誌の執筆は依頼が届いて執筆する事が大半です。しかし、投稿を受け付けている商業誌も多いので雑誌の投稿規定の欄をチェックしてみて下さい。
学会発表
雑誌への掲載ほどではありませんが、学術集会での発表は履歴書のスペックを上げるためには良い経験です。養成校を卒業してから毎年1回以上出来ていればベストでしょう。
学会発表は大変ですが栄養士としての知識以外にも得られるモノは多いのでぜひ取り組んで下さい。
この項目で示したあなたの「資格」「専門雑誌への記事掲載」「学会発表」を職務経歴書に箇条書きできるとスペックが上がっています。他にもあるかもしれません
「情熱をもって仕事していました」等の抽象的な作文はライバル達も書いています。頑張っているのは採用側も分かっていますので、選考側としては具体的な実績(スペック)を知りたいのです。
筆記試験:チェックすべきガイドラインと問題集

- 糖尿病治療ガイド 最新版
- CKDガイドライン 最新版
- 大量調理マニュアル
- 日本静脈経腸栄養学会 認定試験基本問題集
- NST専門療法士認定試験過去問題集
- 管理栄養士国家試験の過去問題集
上記をチェックしておけば、ほぼ対応可能でした。驚いたのは「日本静脈経腸栄養学会 認定試験基本問題集」をそのまま出題した病院がありました。採点や問題作成の管理を考えると出題側としては流用するのが合理的だからだと思います。
すべてをチェックして把握するのは大変です。診療ガイドラインは栄養・食事の部分だけでも十分ですし、管理栄養士国試の過去問は臨床栄養学と給食経営管理論の領域だけで十分と思われます。
面接:今の仕事を説明する力

今、自分自身が働いている内容を説明できれば良いと思います。面接では①事務部門の人事担当、②栄養部門の管理職が面接官になります。それぞれに対策しておけばスムーズに面接が進められ好印象です。私が受けた質問を基に対策を示していきます。
事務部門の人事担当
一般的なマニュアル型の質問が多かったです。例を挙げると「既卒のあなたを雇うメリットを教えてください」「長所を教えて下さい」等です。転職活動サイトや本に載っている一般的な質問の回答を準備しておけば対応できます。
栄養部門の管理職
実務を経験していないと答えられない栄養士業務の質問が多かったです。例を挙げると「栄養スクリーニングとNST介入の流れを教えてください」「栄養指導の件数は何件こなしていましたか?」等です。これらの質問は普段の仕事をするだけではなく、職場の背景を知っていると厚みのある回答が出来ます。つまり、具体的な数字を添えて回答することです
これらが出来るようになる為には、普段から自身の仕事の目的や職場の実績を知っておく必要があります
質問と回答例
質問:「今勤務している病院の栄養スクリーニングとNST介入の流れを教えてください」
回答:「スクリーニングはSGAを用いて入院時の全患者に行われます。高度不良と判定された患者のうち、除外基準に該当しない患者がNST対象となります。日々の入院患者は○人、そのうち約〇%がNST対象となります。私はそのうち〇件を担当してきました。」
面接は確認作業だとよく耳にします。履歴書と筆記試験で候補の順位は決まっているというのです。したがって、面接はマイナスポイントが無いようにする事が大切です。
実際の質問内容は下記の記事を参照下さい(2019.11.9追加)

テクニックと心構え
私が転職活動をしていた時のテクニックと心構えを示します。参考までに
- 職したい病院のホームページを全てブックマーク、一週間ごとにチェック
- 即送れる履歴書セットを常備
- 筆記試験はおわってすぐメモアプリに問題を記録。次の試験の対策に
- 40歳まで挑戦し続けてダメだったら諦める。明確な諦めポイントを設定
- 転職準備は万端で、機会があれば即対応できる努力
- 面接で落ちても、病院ニーズに合わなかったと考える。ただし、回答の反省はする
- 臨床栄養の話題に対応できるよう自己研鑽(論文、学術集会、研究会、専門誌)
- 転職サイトに登録して情報集めと作法の確認は行う
臨床栄養にもトレンドがあります。情報収集は雑誌を読むのが一人でも出来るので手っ取り早いですね。

給食会社等で働いており、今回の記事に示された事が出来ない方は、いきなり大病院の正規職員を目指すのは難しかもしれません。精神科病院・療養型病院・産休の代替要員等は比較的募集が多めで採用されやすいです。まずはこういった所で経験を積んではいかがでしょうか。
以上、私の転職活経験をもとに対策をまとめてみました。
マナーは転職サイトに登録したり、就活本に一度目を通しておく程度で良いと思います。
転職は新卒とは違い明確な期限がありません。不明確な未来に対して継続した努力が必要となってきます。がんばりましょう
おわり