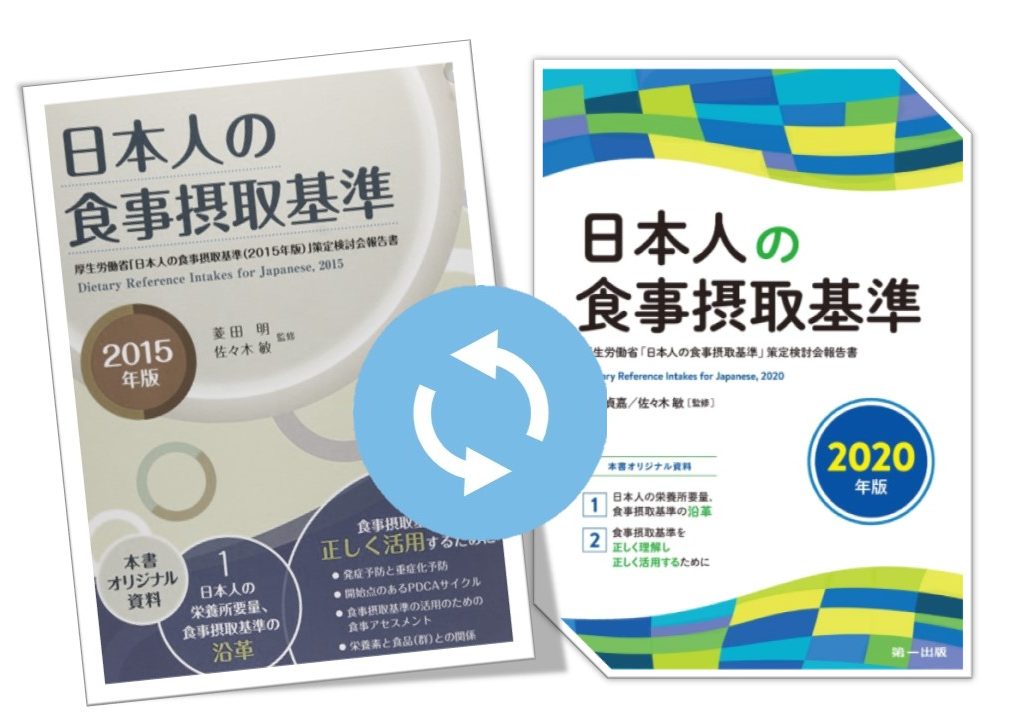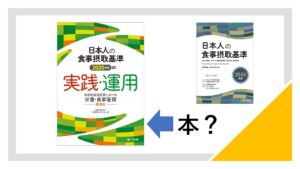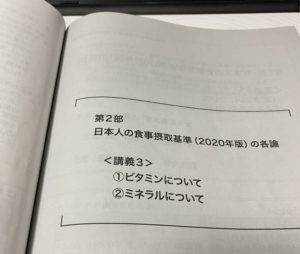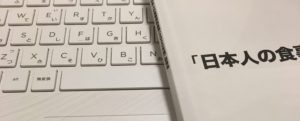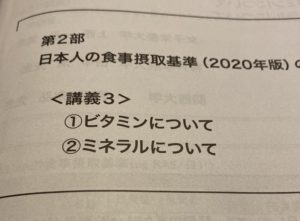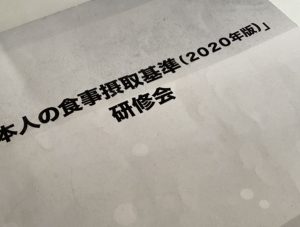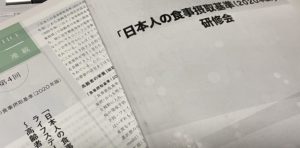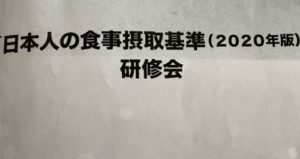2020年度版の日本人の食事摂取基準が発表されたけど、厚生労働省のホームページで読めるから、2,800円も出して買う必要は無いよね・・・?。でも持ってる栄養士は多いけど・・・。
こんな、食事摂取基準の本を買うか迷ってる方向けの記事です。
結論:数字の確認だけなら本は不要。私が買った理由は精神論
✔本記事の内容
・書籍の付録【何が解決できるのか】
・書籍とホームページで読む事の何が違う?
・精神論
この記事を書いている私は、食事摂取基準【2020年度版】の書籍を購入して読みました。読んだ立場から、購入を迷っている方向けに示していきます(買った側ですが)
書籍の付録【何が解決できるのか】
書籍とホームページの一番の違い、それは書籍には付録が付いているという事です。
付録は合計40ページ。全20個のトピックスがあり、1トピックに2ページが使われています。他にも食事摂取基準の沿革が6ページ。
私が有益だと感じたトピック
- 献立で栄養量の数値誤差はどこまで許容できるか
- 「野菜は一日〇〇g」をそのまま説明するのがダメな理由
- 栄養の日間変動・過少申告の影響がどれくらい大きいか
献立で栄養量の数値誤差はどこまで許容できるか
付録で一番有益だったのがこのトピック。献立作成を行うときに「カロリーは5%の誤差まで」や「四捨五入して目標値だったらok」など栄養量の許容範囲を施設ごとに定めていると思います。場合によっては明確な数字は無く、感覚的に業務を行っていて苦しんでいる栄養士も多いのではないでしょうか。
この問題に対して根拠をもって回答がされています。ちなみに、付録における許容範囲は±5%です。食事摂取基準の数値が丸めで定められている為です
「野菜は一日〇〇g」をそのまま説明するのがダメな理由
「野菜は1日350gです。片手いっぱいの野菜が100gだから・・・」と野菜の必要性について栄養カウンセリングで説明する事は多いと思いますが、なぜ350gなのか・代替案は作れるか 等が理解できます。
栄養の日間変動・過少申告の影響がどれくらい大きいか
栄養カウンセリングで相談者から食習慣を聞き取り、場合によっては修正を試みる事が多いと思いますが、そもそもの相談者の申告内容には(悪気が無くても)誤差が大きいという話で、その根拠が理解できます。
日間変動・過少申告については食事摂取基準の本文中にも触れられていますので、付録が必須とは思いませんでしたが
書籍とホームページで読む事の何が違う?
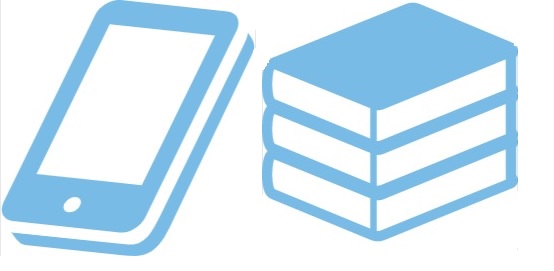
内容は同じなので、一般的に言われている電子書籍と紙書籍の違いがメリット・デメリットになるのではないでしょうか。
思いつく違いは下記
- スマホで読める。スペース・手軽さ・照明機能・メモ機能等
- 書籍は2,800円、ホームページは0円
- ホームページは検索ができる
精神論【栄養士なら買っとく?】
書籍を買った私が感じた中身以外のメリット。
- カラーが見やすい
- 栄養の全体像がつかみやすい
- 所有欲を満たせる
やはり内容に違いはなく、ド忘れした栄養素の数値はホームページですぐ調べられますので、「書籍じゃないといけない」という理由はありません。
おしまい