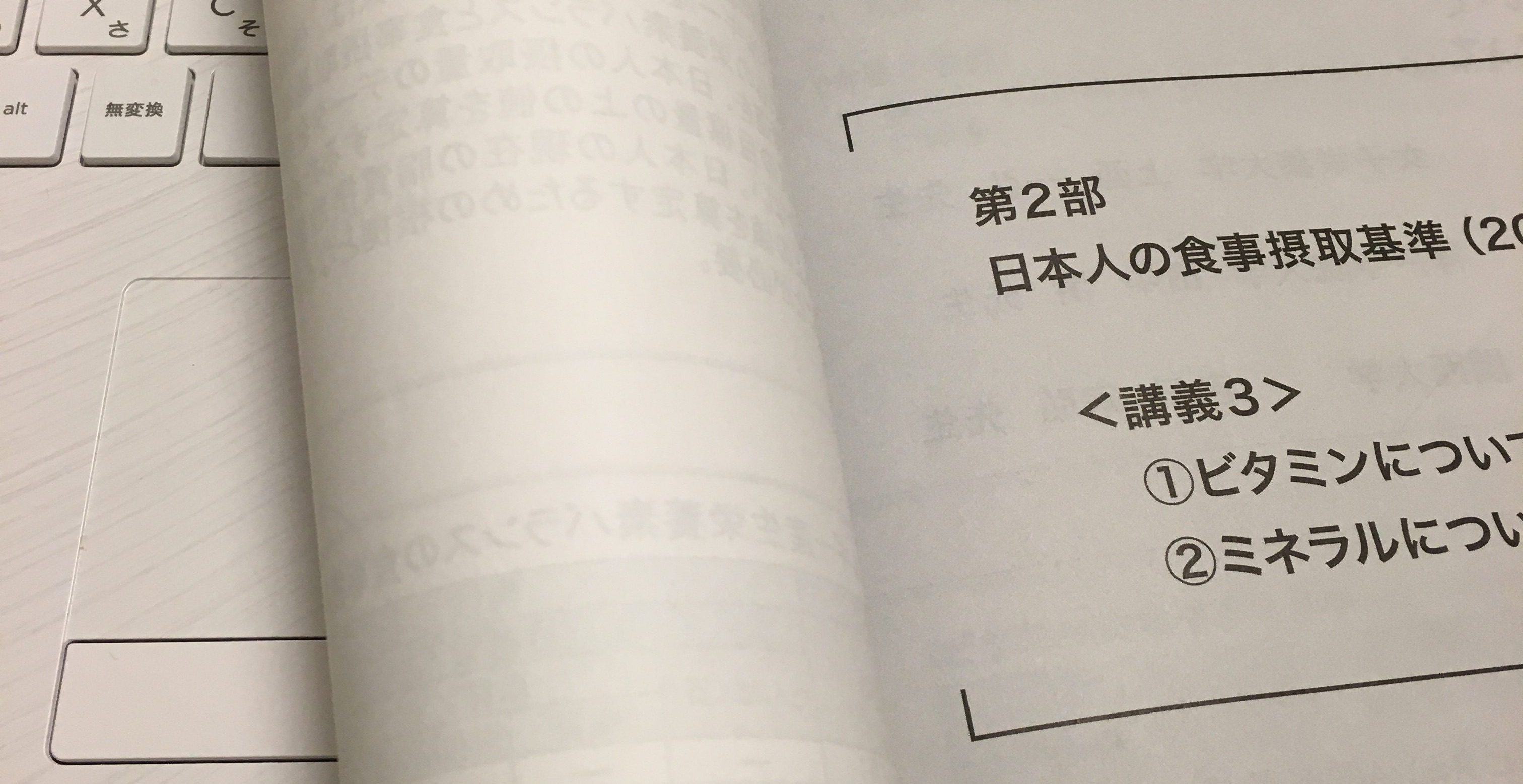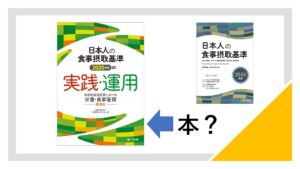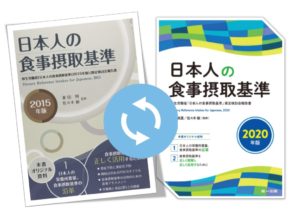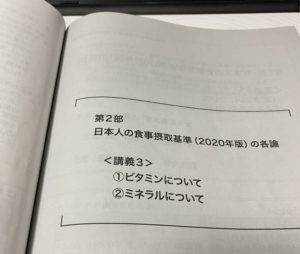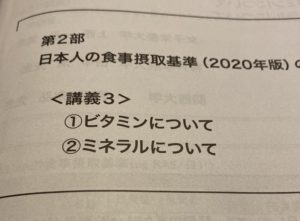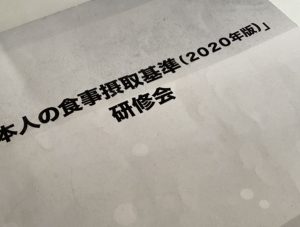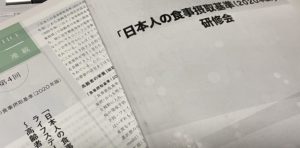食事摂取基準の2020年度版が出るし、改定か所を全部調べる時間がない。忙しくて読めない。こんな悩みを抱えている栄養士さん向けの記事です。
食事摂取基準2020のビタミン(A・D・E・K)だけをまとめます。エネルギー・食塩等、ほかの栄養素が知りたい方はこちら。
あわせて読みたい

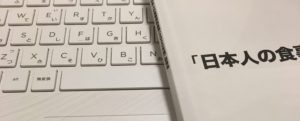
【目標・目安量】食事摂取基準2020まとめのまとめ
食事摂取基準の2020年度版が出た。改定か所を全部調べる時間がない。忙しくて読めない。こんな悩みを抱えている栄養士さん向けの記事です。 過去に私がまとめた記事をさ...
この記事だけでは食事摂取基準の全てを把握できませんので、詳細は厚労省のHPをご確認いただくか、書籍 を購入下さい。
✔本記事の内容
食事摂取基準2020年度版 改定か所のまとめ
・ビタミンA
・ビタミンD
・ビタミンE
・ビタミンK
目次
ビタミンA

男性
| μg RAE/日 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐用上限量 |
| 0~5か月 | 300(目安量) | – | 600 |
| 6~11か月 | 400(目安量) | – | 600 |
| 1~2歳 | 300 | 400 | 600 |
| 3~5歳 | 350 | 450↓ | 700 |
| 6~7歳 | 300 | 400↓ | 950↑ |
| 8~9歳 | 350 | 500 | 1200 |
| 10~11歳 | 450 | 600 | 1500 |
| 12~14歳 | 550 | 800 | 2100 |
| 15~17歳 | 650 | 900 | 2500↓ |
| 18~29歳 | 600 | 850 | 2700 |
| 30~49歳 | 650 | 900 | 2700 |
| 50~64歳 | 650 | 900 | 2700 |
| 65~74歳 | 600 | 850 | 2700 |
| 75歳以上 | 550 | 800 | 2700 |
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書より出典
↑:2015年版からの増加 ↓:2015年版からの減少
・50歳以上の年齢区分が新設 ・推奨量・耐容上限量の一部が変更された
女性
| μg RAE/日 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐用上限量 |
| 0~5か月 | 300(目安量) | – | 600 |
| 6~11か月 | 400(目安量) | – | 600 |
| 1~2歳 | 250 | 350 | 600 |
| 3~5歳 | 350↑ | 500↑ | 850↑ |
| 6~7歳 | 300 | 400 | 1200↑ |
| 8~9歳 | 350 | 500 | 1500↑ |
| 10~11歳 | 400 | 600 | 1900↑ |
| 12~14歳 | 500 | 700 | 2500↑ |
| 15~17歳 | 500 | 650 | 2800↑ |
| 18~29歳 | 450 | 650 | 2700 |
| 30~49歳 | 500 | 700 | 2700 |
| 50~64歳 | 500 | 700 | 2700 |
| 65~74歳 | 500 | 700 | 2700 |
| 75歳以上 | 450 | 650 | 2700 |
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書より出典
↑:2015年版からの増加
・50歳以上の年齢区分が新設
・推定平均必要量・推奨量・耐容上限量の一部が増加
- ビタミンAは肝臓内に蓄えられている。肝臓内のビタミンAの最小貯蔵量を維持するために必要な量を推定平均必要量として策定
- 成人の耐容上限量は肝臓へのビタミンA過剰蓄積による肝障害を指標にして算定
ビタミンD

| μg/日 | 男性目安量 | 男性耐用上限量 | 女性目安量 | 女性耐用上限量 |
| 0~5か月 | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
| 6~11か月 | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
| 1~2歳 | 3.0↑ | 20 | 3.5↑ | 20 |
| 3~5歳 | 3.5↑ | 30 | 4.0↑ | 30 |
| 6~7歳 | 4.5↑ | 30↓ | 5.0↑ | 30↓ |
| 8~9歳 | 5.0↑ | 40 | 6.0↑ | 40 |
| 10~11歳 | 6.5↑ | 60 | 8.0↑ | 60 |
| 12~14歳 | 8.0↑ | 80 | 9.5↑ | 80 |
| 15~17歳 | 9.0↑ | 90 | 8.5↑ | 90 |
| 18~29歳 | 8.5↑ | 100 | 8.5↑ | 100 |
| 30~49歳 | 8.5↑ | 100 | 8.5↑ | 100 |
| 50~64歳 | 8.5↑ | 100 | 8.5↑ | 100 |
| 65~74歳 | 8.5↑ | 100 | 8.5↑ | 100 |
| 75歳以上 | 8.5↑ | 100 | 8.5↑ | 100 |
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書より出典
↑:2015年版からの増加 ↓:2015年版からの低下
・50歳以上の年齢区分が新設
・1歳以上の目安量が増加
・6~7歳の耐容上限量が男女とも低下
- 報告が乏しく、推定平均必要量・目標量は策定困難。骨折リスクを上昇させないビタミンDの必要量にもとづき、目安量を設定
- 目安量:アメリカ等の推奨量から日照により皮膚で産生されると考えられるビタミンDを差し引き、摂取実体をふまえ策定
- 耐容上限量:高カルシウム血症を指標として、負荷試験の結果にもとづき算定
- 長期入院で日照が無ければ不足8.5μg/日でも不足のリスク
- フレイル予防を目的とした量は科学的根拠なく、設定見送り
ビタミンE

| mg/日 | 男性目安量 | 男性耐用上限量 | 女性目安量 | 女性耐用上限量 |
| 0~5か月 | 3.0 | – | 3.0 | – |
| 6~11か月 | 4.0 | – | 4.0 | – |
| 1~2歳 | 3.0↓ | 150 | 3.0↓ | 150 |
| 3~5歳 | 4.0↓ | 200 | 4.0↓ | 200 |
| 6~7歳 | 5.0 | 300 | 5.0 | 300 |
| 8~9歳 | 5.0↓ | 350 | 5.0↓ | 350 |
| 10~11歳 | 5.5 | 450 | 5.5 | 450 |
| 12~14歳 | 6.5↓ | 650 | 6.0 | 600 |
| 15~17歳 | 7.0↓ | 750 | 5.5↓ | 650 |
| 18~29歳 | 6.0↓ | 850 | 5.0↓ | 650 |
| 30~49歳 | 6.0↓ | 900 | 5.5↓ | 700 |
| 50~64歳 | 7.0↑ | 850 | 6.0 | 700 |
| 65~74歳 | 7.0↑ | 850 | 6.5 | 650 |
| 75歳以上 | 6.5 | 750 | 6.5 | 650 |
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書より出典
↑:2015年版からの増加 ↓:2015年版からの低下
・50歳以上の年齢区分が新設 ・目安量の一部が変更
- データ不十分にて日本人の摂取量の中央値をもとに目安量を設定
- 耐容上限量は出血作用に関するデータにもとづき算定
ビタミンK

| μg/日 | 男性目安量 | 女性目安量 |
| 0~5か月 | 4 | 4 |
| 6~11か月 | 7 | 7 |
| 1~2歳 | 50↓ | 60 |
| 3~5歳 | 60↓ | 70 |
| 6~7歳 | 80↓ | 90↑ |
| 8~9歳 | 90↓ | 110↑ |
| 10~11歳 | 110↓ | 140↑ |
| 12~14歳 | 140↓ | 170↑ |
| 15~17歳 | 160 | 150↓ |
| 18~29歳 | 150 | 150 |
| 30~49歳 | 150 | 150 |
| 50~64歳 | 150 | 150 |
| 65~74歳 | 150 | 150 |
| 75歳以上 | 150 | 150 |
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書より出典
↑:2015年版からの増加 ↓:2015年版からの低下
・50歳以上の年齢区分が新設
・目安量の一部が変更
- データが十分に無く、健常人を対象にした観察研究をもとに目安量を設定
- 目安量:納豆を非摂取者においても明らかな健康障害は認められていない事を踏まえ、納豆の非摂取者の平均値をもとに設定
ビタミンDは日照によって皮膚で生産されるので、実験データを基に変更されています。栄養はヒトの体を考えるので、口から入る食物だけ見ていてもダメなようです。
つづく